彦坂尚嘉 オーラル・ヒストリー 第1回
2012年3月26日
立教大学 彦坂尚嘉研究室にて
インタヴュアー:富井玲子、足立元
書き起こし:成澤みずき
公開日:2017年7月23日
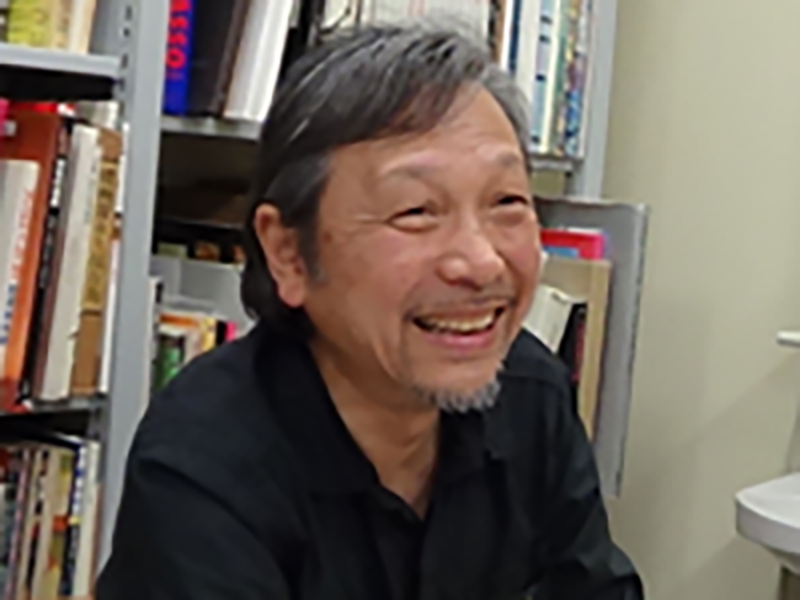
現代美術家・美術史評論家
東京都出身。1969年美術家共闘会議(美共闘)の結成に参加。1970年多摩美術大学美術学部絵画科(油画)中退。1971年雑誌『美術史評』(第一次)創刊を主導。1975年第9回パリ青年ビエンナーレ出品。1982年ヴェネツィア・ビエンナーレ出品。1982~1983年文化庁新進芸術家在外研修員としてアメリカ・フィラデルフィアに留学。1987年サンパウロ・ビエンナーレ出品。1999年グローバル・コンセプチュアリズム展(クイーンズ美術館ほか)出品。2000~2009年 第1回~4回越後妻有トリエンナーレ出品。2013年あいちトリエンナーレ出品。2008~2013年立教大学大学院文学研究科・比較文明学専攻特任教授。主な著書に『反覆/新興芸術の位相』(田畑書店、1974年)、『彦坂尚嘉のエクリチュール——日本現代美術家の思考』(三和書籍、2008年)。主な共著に「年表・現代美術の五〇年 上・下」(『美術手帖』1972年4月号、5月号)、『3・11万葉集 復活の塔』(彩流社、2012年)など。
今回のインタビューでは、生い立ちから69年の美共闘結成までを中心に、芸術の評価・格付けの根源的な問題までを縦横無尽に語られている。
富井:2012年3月26日彦坂尚嘉さんにインタビューします。場所は立教大学の彦坂さんの研究室です(彦坂氏は、2008~2013年の5年間、立教大学大学院比較文明学の特任教授を務められました)。
本日はお忙しいところ、ありがとうございます。オーラル・ヒストリーのインタビューのメソッドとして、方法論として、作家の生い立ち、及び家族のことなどから、どういう形でアーティストになっていったかということから始まりますので、今回もその形でお願いします。
まずは1946年6月26日、東京でお生まれでしたか?
彦坂:そう出自の問題が大きいのです。だから重要なことは……、1946年6月26日に「生まれた」という記憶は、私には無いわけですよね。
富井:そうですね。
彦坂:自分が出生したという記憶、産湯に浸かったとかそういう記憶は三島由紀夫の様には持っていないのです(笑)。
そういう不確かさが私には悲劇だったのですね。自分が生まれた年とか、親とか、国や地域を、自分が選択してないわけです。全く受動的ですよね。そういう茫漠とした中で、いつの間にか存在してきているわけです。その不確かさを、当たり前と考えて、自明なものとしておくことができなかった。いや本当の事を言えば、祖母と母がつくったストーリーを信じて育ったのです。そのストーリーが嘘だったので、私にとっては非常に深刻な精神分析的な病になってしまう運命を背負っていたのです。本当に6月26日に生まれたのかっていうのも、まあ私の場合、特にそれが何か日にちを偽って戸籍に書いたとか、そういう人もいるではないですが……。
富井:ありますね。(届けを)遅らせたとか。
彦坂:そういうことは、母親や祖母からも全く聞いていません。しかし有名な戦後文学者の井上光晴のように、ご本人が生い立ちや経歴について意図的に嘘をついてらっしゃるとかそういう例はあるとは思いますけど。別にそういう虚言癖は私には無いです。
しかし一つの物語はあるのです。1945年8月15日に実の両親がセックスをして、10月10日たつと、1946年6月26日になって、私が生まれたというものです。日本の敗戦と、私の誕生を強く結びつけているのですね。これは私が一人で作った神話です。
もちろん現実は10月10日ではないので、今だと受精してから産まれるまでが平均266日だと言うのですね。つまり9ヶ月10日目ということになります。そうすると、事実は8月15日の反戦の日からひと月立った9月15日に実の両親は、セックスをしているということになる。
ただ、実の父も知らないし、自分では自分の育った家族生活に確証が無いわけですよね。(生まれたという)証拠が特に(ある)っていうのも難しい問題です。だからそれは例えばそういう茫漠とした中で生まれて来たということが、私という美術家の制作の方法になってしまうくらい大きかったわけです。そういうことが、今度は拡張して日本の現代美術の出自を確認しないと、気が済まなくなるのですね。さらには、美術や芸術の「原点」を問い詰めていくことが、制作行為になっていく。
付随的に言いますけど、私は「日本ラカン協会」という学会に入っていますけれども、昨日もシンポジウムがあったのです。ジャック・ラカンという精神分析者は、「人間には自分自身が見えない」ということをすごく重視したのです。
お互いに他人は、見えていますけれど、自分の顔は見えないのですよね。
自分の身体の外形のフォルムを把握する内在的な感覚も無いわけです。自分の身体のトータルな輪郭って見えないわけです。他者は明確に輪郭を持っていますけれど、自分には、自分の身体の輪郭すら、内部感覚からは把握できない。
鏡を見るとか、写真に撮って見るということをして、間接にしか確認が出来ない。そういう不確かな不安や恐怖が、私には非常に重要なことなのです。
ジャック・ラカンという哲学的な精神分析家は、そういう自分自身が見えないっていうことを、人類史の中で初めて直視した人物なのです。人間というものは、鏡を見て、自分の自我をでっち上げているという指摘をしたのです。
私という美術家が、ラカンを高く評価するっていうことも、この人間の自己確認不能性を、自覚化をした人物だったからです。
富井:そうするとお母さん、お父さんは、見える形でいつ頃か、彦坂さんの意識の中に入ってきたわけですよね。
彦坂:母親をどこで見たかっていう記憶も無いですよね。ただ、父親はあるのです。父親はある時に、隣の布団に寝ているのがふと見えて、眼鏡取った顔が、横にあって、そのヌルッとした異様さを、今でも覚えています。突然として父親は出現したのです。
富井:それは彦坂の(実の)お父さんですね。
彦坂:彦坂の実父ではなくて、狩川徹です、だからその、義理の父です。血縁関係はありません。戸籍上だと義兄になっているのです。だからそれが不意に出現したっていうのは覚えている。
後から、実は1979年に西武美術館で「木との対話展」って(展覧会を)やりますけど、(「Art Today ’79 木との対話展」西武美術館 1979年3月3日~3月27日)、私にはその時に選ばれたこと自体がかなりのプレッシャーになっていたのです。そのプレッシャーの中で、毎晩部屋を暗くして、寝床に入って、目をつむって自分の心の中にサイコダイビングして、過去の記憶をずっと探していくのですね。つまり自分で精神分析をしていったのです。
サイコダイビングというのは、夢枕 獏という小説家が、サイコダイバー・シリーズ「魔獣狩り」を書いて一躍ベストセラー作家となったのですが、私もそれを読んでいた影響です。自分で自分自身の心の中で飛び込んで、過去に向かって記憶の中を泳いでいくのですね。そういう作業をすると、トラウマっていうか、嫌な思い出があると、身体がパーンと跳ねるのです。電気にうたれたみたいに、痛みに反応して、寝ている体が布団から跳ね上がるのです。
こういう話をその時は友達だった奥山民枝さん(1946−)という画家に(したら)、ものすごく異常だっていう反応をされたのですだけど、私からするとそれは別におかしくはないのです。アメリカだったら精神科医(Psychiatrist)にかかってやるような作業を、自分一人でやっているっていうだけですから。
富井:そういう時にそういうお父さんの記憶が、戻って来たということですか。
彦坂:いや、父親に……。だから最初の「木との対話展」の搬入の日の朝に、母親に、とにかく「父親に抱かれた記憶が無い」って言ったわけです。
富井:なるほど。
彦坂:それを思い出すまでに「木との対話展」の1979年までの約30年の年月を必要としたわけですね。そうすると母親が、「実はあれはあなたのお父さんじゃなくて……」っていう話をしたわけです。
富井:その場合は、お父さんって今言っているのは、お母さんの旦那さんということですよね。
彦坂:そうそうそう。
富井:それが彦坂さんですよね。
彦坂:それが彦坂さんじゃなくって狩川徹。
富井:そうでした。また間違えました。
彦坂:だからその言い換えると、その制作をしていく時でも、「木との対話展」に向かってこちらが最初やろうとしたプランの大半はできなかったですけど、自分の心の中にサイコダイビングせざるをえないような、ものすごいプレッシャーがあって、わけのわからないものと対峙する心理的な対象化の作業が必要だったのです。
そういうわけのわからない無意識との戦いというか、抑圧されて隠された記憶との戦いが、私の美術家としての制作には、ずーっとくっついてきているわけです。
フロイトがいう「無意識」というのは、ユングの言う「集合無意識」と同一のものなのです。フロイトに言わせると、個人だけの無意識は無いのであって、無意識というのは社会的歴史的な共同体の無意識なので、だから「集合無意識」などとわざわざ言う必要は無いというのです。個人だけの無意識は無いのです。個人の無意識は社会意識、そして歴史意識の中にあるのです。無意識というのは抑圧されているのですが、その抑圧を取り除く特別な操作をしないと、意識化が可能にならないのです。ですから私は特別な操作活動として、日宣美粉砕闘争に参加してアジテーションを展開したり、日展粉砕闘争を組織したり、800頁の『年表:現代美術の50年』の編纂になったり、美術批評の分析や、現在の言語判定法を使った芸術分析をしているのです。本人は必死の作業なのですが、他人は理解不能なので、まあ、多くの人に悪意に満ちた人間として受け取られて嫌われることになったのです(笑)。
だから私の様に私生児ではなくて、普通に生まれて、普通に健康に育った方というのは、私のようなさまざまな疑問が沸かないのかもしれません。私から見ると、みんな驚くほどに抑圧された強い自明性を生きているように見えます。
例えば岸田秀さんってフロイト系の精神分析家がいますよね、『ものぐさ精神分析』(1978年)というシリーズを書いてらっしゃる。岸田秀さんの場合は、問題だったのは義理の母です。彼は貰われっ子で、義理のお母さんからものすごい溺愛を受けたわけですね。そういう中での心理的葛藤が強くあって、そのためか、それが転移して、太平洋戦争で沈没した軍艦の日本兵たちが海に投げ出されて溺れて死んでいく様が、彼の心にまとわりついてくるのですよね。そういう問題がある。それはだから私の中でもそうですけど、やっぱり太平洋戦争と非常に深く記憶が結びついているのですよね。
足立:太平洋戦争の直後に生まれてらっしゃいますか?
彦坂:太平洋戦争の直後に生まれているからっていうことが、大きいと思いますけど、こだわるというか、例えばひめゆり部隊に対してすごくこだわったから、沖縄に3回行っていますけど。最初行った時は、空港でレンタカーを借りて、夜だったのですけど、ひめゆりの塔を見に行って、誰も案内なくて、もう道もよくわかんないのですよね。月光だけの闇の中を、激戦地(沖縄戦跡国定公園/平和祈念公園)をさまよって、たくさん塔が建っていて、ようやくひめゆりの塔を見つけて、それが非常に大きくて。それを拝んで帰って来て、呼んでくれた琉球大学の教授と話したら、「怖くなかったのですか?」って言うから、そんなことないですよ、だって死者たちを弔いに来ているのだからね、私は怖いわけは全然無いですよって申し上げた。そしたらその奥さんのお母様っていう方がひめゆり部隊の生き残りの人だったのですね。それでお会いできたのですけど。生き残ったということに、深い罪の意識を持っておられた。
あと2度目に行った時には、ひめゆり部隊が逃げた経路を全部辿っていきました。防空壕ごとに、飛び飛びに逃げているのです。防空壕の中にはまだ遺骨が入っています。全然遺骨収集ができていないのです。防空壕は壊れやすくて、危なくて、遺骨収集ができない。ですから、入り口に、お花とお線香をあげてずっと回っていったのです。その時はホルベインという絵の具屋さんがありますが、ホルベインがPR雑誌で『アクリラート』という雑誌を出していまして、それの編集者に沖縄の建築と沖縄の美術を扱おうという企画を私が出して、それが採用されて実現したのです。それで実行したのですが、十分にそのひめゆり部隊が逃げた経路を辿るという話をしないでやったわけですね。そしたら、「何をしているのでしょうかね、何をしているのでしょうかね」って言われて(笑)、そしたら東京に帰ったらその編集者は「悪霊が憑いた」って言いはじめて、耳が聞こえなくなって、それで本当に亡くなられちゃったのですよね。面会を申し込んでも会ってもらえなくて、それも病名もよくわからなかったのですけど。お通夜も、お葬式も、私だけではなくて、他のアーティストもみんな呼んでもらえなくて、不審な亡くなり方をなさいました。
何て言うのかな、その方の死は必ずしも私の責任だとは思わないですけども、沖縄に関してはある種わけのわからない脅迫的な神経症みたいなものが、私のどっかにくっついていまして、それの根幹は、自分の父親そのものがわからないと言うことに原因があるのでしょうね。しつこく何かを探求していくのです。美術にしても、絵画や彫刻にしても、芸術にしても、深い所まで疑って、サイコダイビングしていかないと気が済まないのです。
だからさっきおっしゃったように1946年6月26日っていうのを、今度は外から、言葉で考えていかざるを得ない訳です。歴史的事実と言われていることと、見えないっていうこととの間を追いかける。言語化されて普通に客観的な事実として歴史に記述されていることの隙間というか、歴史的記述と不可視であることの交錯を追いかけていく。なぜ彦坂尚嘉は、美術家になったのですかっていうことのひとつの問題は、そういう出自の問題なのです。
富井:それを聞き出していくのが今回の私たちの目的みたいなことでもあるわけですけども。社会との関わりのこととか、デビューのこととか、大分ちょっとまだ先になるので、少しお話戻していただいて、一応皆さんにご家庭の、例えば芸術環境ですとか、どういう形で美術に親しんでいたのかという非常に素朴なことを聞くんですけど。
彦坂:(写真を出して)これ、私でございまして、一応、親は「すごく可愛かった」って言う訳ですね。
富井:いや可愛いですよ。
彦坂:それで私の長女がいるのですが、その子も非常に生まれた時は可愛かった。次女は母親に似ていて、カリビアンの様な野生の精悍さがあって、これもかわいかったですが、二人は違っていておのおのの個性がありました。
富井:長女のお嬢さんは、彦坂さんに似てるんですか。
彦坂:そういうなら似ていると思いますね。
富井:いいですか、撮らせていただいて。
彦坂:これを撮影した時は覚えているのです。
富井:これは何歳くらいですか。
彦坂:わかんないですね。
富井:一つ、二つ目くらいですかね。なるほど、覚えてるんだ。
彦坂:うん、覚えていますね。
富井:ハイカラな椅子ですね。これは写真館ですよね。
彦坂:写真館ですね。
富井:この写真には歳が入ってきますね、4歳とか。
彦坂:これ、祖母ですね。
富井:そっちはおばあさんですか。4歳はおばあさんと一緒ですね。これは、お家ですかね。
彦坂:はい、そうです。世田谷の三宿の二階建ての和風の普通の家ですね。このへんはすぐ側に目黒川という川が流れていて。
富井:随分田舎っぽい感じがするんですけれども。郊外というか。田舎っぽいと言ったら申し訳ないんですけど。
彦坂:その当時は東京といっても、まず世田谷区の池尻の辺というのは、直ぐ側に三菱の工場があったのですね。三菱電機世田谷工場の建物がたくさんあって、「三菱領土」と言われる地域でした。そして私が生まれた池尻、そして小学校4年の時に引っ越した三宿は、陸軍の施設が数多く立地していたのです。(池尻には駒澤練兵場と、野戦重砲兵第四旅団司令部、近衛野砲兵連隊、野戦重砲兵第八連隊があった)。ですから、それに関連して三菱の軍需工場があったと私は思って育っています。だから空襲の標的になるので、三菱の工場の周辺部が強制疎開させられたのですよ。
富井:じゃあ、彦坂さんのお家も。
彦坂:いや、うちは強制疎開の外だったのです。だからうちのすぐ側はみんな壊れた瓦が散乱していて、草がぼーぼーの野原でした。
富井:爆撃でやられていたということですか。
彦坂:爆撃が来る前に壊しているのです。
富井:なるほど、そういうことですか。
彦坂:それで川の向こう側には騎兵山と言って、むかし騎兵第一聯隊が駐屯していたのです。現在は表忠碑という騎兵第一連隊の石碑が建っています。
富井:馬に乗っている?
彦坂:そう。「騎兵山」って言っていました。日清戦争、日露戦争の段階ですね。第一次世界大戦の前には、馬が戦争に使われていて、それが自動車や戦車に代わって行ったのです。それでも騎兵という名前はのこったのでしょう。草がぼうぼうと生えていて、その草の中にトンネルをつくって遊びました。防空壕がたくさんあって、その残っていた防空壕の中に入って、弾が土の中に混じっているんですよね、だから弾拾って集めていました。
富井:(写真を指して)こちらは、お母さんですよね。
彦坂:そうですね。
富井:ふっくらとしたお顔で。彦坂さんとそっくりみたい。なんか並んでらっしゃるとそう思います。(笑)なんかこう、親子みたいな感じで並んでらっしゃいますけれども。綺麗なお母さんで。
彦坂:親子ですよ(笑)。子供の頃の自分って、ずいぶん違うのですね。ただもうこの頃の写真ですと、自分だって言う風に認識するのが難しいですよね。アトリエを一緒にしている糸崎公朗(1965年—)さんが「彦坂さんの顔は、どんどん変わっていって、変化して行く」と指摘されていますが、私の人格は成長してきましたから、顔も変化するのです。
富井:これは妹さんですね。
彦坂:これ、妹。妹も突然として出現するわけですね。
富井:彦坂さんの意識の中にですか?
彦坂:意識の中にというより、はっきり覚えていますけれど、つまり「妹が来る」ということを言われたわけですよ。来た時のことを覚えているよりも、「明日来るよ」って言われたことを強く覚えています。それは狩川徹さんの、最初に結婚した奥さんが亡くなってしまって、子どもが残っていたわけですね。だから私の母親とは血縁関係がないわけですね。
富井:なるほど、そういうことなのですか。
彦坂:だから全く血の繋がっていない妹ということになりますね。戸籍上もさっき言い忘れましたけど、彦坂家の方に僕は入っていて、父親は狩川ですから、だから彦坂家の跡継ぎがいなくなるから、「最初の生まれた子どもを彦坂家の跡継ぎにしたのだよ」、という風に言われて育つわけです。
富井:彦坂というのは……狩川さんは狩川さんですから、お母さんの方?
彦坂:だから彦坂家というのは宇都宮藩の家老の家で、宇都宮藩というのは、宇都宮戦争(宇都宮城の戦い、1868年)というのを経てるわけですね。それで半日くらいで壊滅しているわけですね。
富井:幕末維新の時ですね。
彦坂:はい。これも実を言うとですね、最初からそんなこと知っているわけではないのですよね。調べていく中でわかってきたということであって、もともとは知りませんでしたから。私は実を言うと長い間ですね、明治維新の時に、官軍と賊軍がいるじゃないですか。私は賊軍の側にいると思っていたのですよ。
富井:宇都宮戦争の時ですか。
彦坂:はい。宇都宮藩というのは当然幕府側だと思っていたのです。ところが調べていくとそうではなくて、官軍側にいて、それで結局幕府の最後の軍隊っていうのが、フランス軍の軍事顧問が訓練したもので、フランス式軍事訓練をされた旧幕府歩兵部隊が二千から三千いて、それを新撰組の土方歳三が率いて、函館に向かって北上をはじめるわけですね。それとぶつかって敗北した。宇都宮城というのはわずか1日でやられてしまっているのです。そこで彦坂という家老の家というのは壊滅しちゃうのですね。それで位牌をもっておじいさんが東京に逃げて来たということなのです。だからそういう一種の滅亡の系譜なのです。
祖母の方の静(シズ)の家系も、同様に滅亡しています。これは小さいときからそういうことを聞かされていたわけですけれど、大磯の三宅という大庄屋の家でした。祖母静のお父さんお母さんが小さい時亡くなって、みるみる三宅家が滅亡していった。だからその祖母に私は育てられるのですけど、だから祖母の、そういう名家に生まれながらも滅亡していった、衰退していったというその想いみたいなものが、非常に強く私に影響しています。彦坂仙吉という私の祖父と結婚したのですが、祖父は非常に女遊びをしたみたいで、祖母はそういう女遊びをされたことのトラウマみたいなものが非常に強くあった人でした。生まれ年も巳(へび)年で、その辺の執念深さみたいなものがよくも悪くも私にもともとに付いてくるものがあって、性的なものへの抑圧が強いです。
話を美術にして、最初に絵を描いたのはいつかっていう話をすると、一つはお絵描き教室に行っています。
富井:それはやっぱり、幼稚園とか、幼稚園の前だとかいうと、どれくらいですか。
彦坂:幼稚園は行ってないですね。保育園も幼稚園も行ってない。
富井:行かれてないのですか。
彦坂:はい、行ってない。だからまず一つは、昔つまり結核がものすごく流行るのですね。日本が敗戦すると、栄養失調もあるのでしょうけど、とにかく結核が流行っていって、それに私自身が感染して、腸結核になっている。だから非常に下痢をしていた。それで病弱であったということもあったのだと思いますけど、まあお絵描き教室にやられて。
富井:だから幼稚園に行くかわりにお絵描き教室。
彦坂:当時だから幼稚園というのは、あるでしょうけど、そんなにまだ幼稚園保育園が一般化してなかったのだと思います。
お絵描き教室のことはよくは覚えていませんけれど、薄暗い空間は今も覚えています。個人の家というよりも、昔の狭い都営アパートの団地の小さな空間でした。薄暗い部屋、クレヨンで絵を描いていた。幽霊の、お化けの絵を描いていて、それが随分褒められたのですよ。それを持っていたはずなのだけど、今は見つけられないですね。
富井:褒められたのですか。
彦坂:とにかく私は毎晩お化けを見ていたのです。怖いのですよね。木の廊下があって、それをあるいてトイレに行くわけですけれど、その廊下いっぱいに赤い目のお化けがばっと床に、それこそ《フロアイベント》じゃないですけど、床にいっぱいお化けが張り付いて寝ているのですね。
富井:それは家で?
彦坂:そうです家です。毎晩のようにお化けの夢を見ていました。20歳の時に肋骨を取る手術をしていますが、その時もお化けの悪夢にうなされて、大変でした。医者からは精神的に弱いのではないか?と言われました(笑)。自分でも弱いと思います。1973年には群馬の中之条の禅寺に一年住んでいましたが、その時も檀家の人が死ぬと、それを事前に私は感じて、感じると電話がかかってきて、葬式になりました。アメリカに留学しているときにも、祖母の幽霊が夢に出て来ていて、目が覚めて東京に電話すると葬式の朝でした。だからお化けとか幽霊というのは、昔から私は親しいのです。……。しかしオカルトではないのです。ユングという人物は人格的にはフロイトよりも上であると評価しますが、私はしかしユングには同調しません。フロイトの科学主義の立場を基本に私は考えます。私としては、幽霊の出現も、あくまでも精神分析で考えますし、学問として理解する立場です。
私の芸術分析と称しているものは、「格付け」というのをやりますが、それは163万8400次元というものすごい数字にまでなっているのです。なぜ、そんな巨大な数字になると言うと、それは合わせ鏡の空間なわけです。つまり人間の心が合わせ鏡の様な構造でできている。それが、奥の方で、黄泉の国というか、大霊界までに至っている。つまり心の底には、死んだ人の記憶があって、それが幽霊になって出て来るのです。
しかし子供の頃は、死者の記憶では無くて、不快感とか恐怖があって、それに毎晩苦しめられて幽霊を見ていたのです。
私は、ジャック・ラカンの理論を読んで、人間の心が納得できたのです。ラカンの鏡像理論というものに影響を受けて、それを発展させて、2枚の鏡の構造であることを明らかにしたのです。人間が2枚の鏡の中を生きているというのは、H.G.ウェルズが『世界史概観』の冒頭でも指摘しています。私は糸崎公朗さんの協力を得て、実物の鏡を2枚合わせた装置までつくっています。鏡が2枚あわさっていると、無限に深く、鏡の井戸が写っていって、江戸川乱歩の小説の『鏡地獄』みたいな世界が出現します。江戸川乱歩の小説では、鏡地獄の中では主人公は気が狂ってしまいます。しかし現実の人間は、この鏡地獄の中で、気も狂わないで生きているのです。いや、気が狂っているのかもしれません。その鏡の階層の数が、私の測定では163万8400次元までいっています。原理的にはその先もあるのですが、奥に行くと次第に暗くなっていくので見えないのです。見えないけれどもあるのです。原理的に無限に。
最初は41次元というのを、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザで発見したのです。それで探求して行くと6400次元まで行ったのです。それが現世の最後というか、底ですね。この向こうの6401次元から、心霊研究家の丹波哲郎が主張した大霊界に対応する領域が始まります。
こういう発見というのは、今回の東日本大震災(2011年3月11日)とも深く関わっていたのです。京都に避難したのですが、その時に6400次元にまでたどり着きます。
その東日本大震災の半年経ってから被災地を巡るツアーに参加したのです。ツアーは建築の人たちと一緒に行ったのです。4泊5日で毎日瓦礫の山を見ていると本当にくたびれるし、そうすると更に、世界の奥が見えるようになりました。大地の底で動いているマグマの運動を意識できるようになって、それで5万1200次元まで自覚できたのです。その時に運転していて、5万1200次元の音楽を記憶の中で探したのです。それで、車に積んでいたCDで聞いたのがショスタコヴィッチの交響曲第12番だったのです。ここには5万1200次元がありました。
2枚の合わせ鏡ですので、倍々に増えていって今163万8400次元です。
他人が見たらバカにしか見えないこういう大きな数字が、現実に存在してしまうのです。今のデジタルカメラのイソ感度(ISO)が同じ数字になっているのです。それは、私の周りにいる若い人が、インターネットで検索して発見したのです。
富井:ISO感度も倍々ゲームですか。
彦坂:そうです、ネットによると、163万8400画素のカメラを開発中という話なのです。(現実には、2016年にニコンのD500と言うカメラは、ISO1640000を実現しました。さらにニコンD5は、最高がISO3280000というもので、彦坂尚嘉の想定していた1638400の倍の感度になっています。)
富井:そうなのですか。デジカメですからね、今は。
彦坂: ISO感度が大きくなると言うのは、暗い中でどれだけ撮影できるかっていうことです。だから言い換えると、人間の暗い側面をどこまで認識できるかという内面上の問題とも重なって来るのです。
それで音楽的にもそういう暗いものを探して見つけたわけです。一番分かりやすいのはニルヴァーナ(Nirvana)というアメリカのロックバンド(1987年結成、1994年活動停止)ですけど。ニルヴァーナっていうバンドが1991年のソビエト崩壊の時に出現して、「スメルズ・ライク・ティーン・スピリット」という曲を大ヒットさせます。この曲が超次元から163万8400次元あります。このことが近代の終わりを象徴するものでした。つまり近代というのは第50次元までのものなのです。たとえば現代作曲家のブーレーズの1955年のル・マルトー・サン・メートル(Le marteau sans maître, 主なき槌)は、超次元から第50次元までの曲です。代表的な50次元までの近代音楽と言えます。この近代の50次元の枠組を破って、163万8400次元という人間の底抜けの闇の世界にまで広がったのが、現在の世界なのですね。ニルヴァーナが描くのはそういう心の闇の世界でした。そういう心の闇が、私の場合には、小児結核に罹患することで、病気による不快感として小さいときから、絡みついていたのです。絵を描くというのは、そういう心の葛藤から生まれたのです。
富井:お絵描き教室っていうのは、自分が行きたいと言ったのか、親が行ったらどう?みたいな形で始められたんですか?
彦坂:親ですね。それでもお絵かきの方は自発性があって、そのおばけの絵は、思うままに描いたのを覚えているのですけどね。
そのあとですが、小学校に絵を持っていく最初の絵を描いているのですよ。それはお家があって、太陽が照っていて、花があってというような、本当にステレオタイプの絵を描いたのですね。すごくきちっとクレヨンで描いている。それを覚えているのですね。この時から、世間体アートで、フォーマリストだった。私の作品というのは精神分析的フォーマリズムなのですね(笑)。
ピアノのほうは「やったら」ってはっきり親が言って、ピアノのお稽古もしていたのです。それは女の先生が家に来て教えてくれました。一応バイエルはあげているのですけどね。義父が、手作りのオーディオ装置でクラシック音楽を聴いていましたので、私自身もだからクラシック音楽を最初から聴いています。けれども、だからといってピアノの曲を聴かされて、すごいでしょうっていう風に誘導されなかったわけですね。単に演奏する練習をさせられるから、ピアノの演奏というものが、何をやっているかっていうことがあんまりよくわかんなかったです。
富井:おばけの絵は、クレヨンですよね。
彦坂:クレパスでした。クレヨンとクレパスは、微妙に違っていて、クレパスの方が柔らかいです。体が弱かったので、家で、一人で動物図鑑や鳥類図鑑を見ながら、その模写を沢山やっていました。それもクレパスだったと思います。
工作少年でもあって、いろいろ作っていましたが、紙で、大きな汽船を作ったときは、義父が驚いた顔をしたので、今もそれを覚えています。それから金属のキットで、ボルトとナットで止めて、いろいろなものを作るオモチャがあって、「エキスパンダー」という名前の様な気がしますけれど、それは好きで夢中で作りました。
小学校一年の時に、初めて油絵を描いています。スケッチ板っていうのが昔あったのですけど、木の板ですね、今は売っていないです。スケッチ板に、花瓶に入ったアジサイの絵を油絵の具で描きました。乾かないうちに、何度もしつこく描き直したので、絵の具が混じってドロドロになって、始末の悪いものになりました。その挫折感というか、トラウマは今も覚えています。このスケッチ版という木の板に絵を描いた記憶が、ウッドペインティングになります。理由は単純なのです。もう一つは、病床で見続けていた天井の杉板です。
富井:それは要するに清原啓一さん(1927年—2008年 日本芸術院会員。光風会常務理事)に師事というか、お教室に行っていたのですか。
彦坂:そう、それで描いていて。
富井:それは自分も油絵したいということだったのですか。
彦坂:いや、これも親ですね。
富井:お父さん、お母さんが。
彦坂:母親ですね。母親が中学校の国語と家庭科の教師をしていたのです。和服を着て、和服といってもウール着物です。和服の生地が、絹じゃなくてウールでできている着物を、ウール着物と言います。戦後でも、和服を普段着として着る女性が多かったのです。和服の人気を押し上げ流行させたのがウールで仕立てられたウール着物であったのです。ウール着物は色彩が美しく、カジュアルで気軽に着られる普段着の和服として、日本中の女性の間で流行となったのです。こういう流行を背景に、私の母は学校に一貫して和服を着て中学校に教えにいった人なのです。
「新しい星」ですね、新星中学っていうのが、246号線の世田谷区三宿にあったのです。三宿交差点を少し入ったところにあって、現在は、池尻中学校と統合されて世田谷区立三宿中学校になっています。
清原啓一先生も、新星中学の教師だったのです。同僚ということで、私の家庭教師になってもらって、家に来てくださって教わっていたのです。
富井:そこで同僚だったのですか。
彦坂:清原啓一先生は、光風会、日展という流れを生きられた官展系の画家でいらっしゃいました。代表作はニワトリのシリーズでした。親は先生の絵は2枚買って、応接間に掛けていたのです。
富井:あの彦坂家にですか?
彦坂:はい。一応ソファーがあって、いわゆる普通の応接間ですね。
富井:やっぱりニワトリの絵ですか。
彦坂:いや、ニワトリじゃなかったですね。池があって、庭があって、そういう風景の絵と、あとは花と花瓶の絵ですね。
富井:じゃあ応接間用絵画みたいな感じですね。
彦坂:はい。しばらくたつと清原先生のアトリエに行って習っていますが、絵筆の代わりにペインティングナイフを使って絵の具をキャンバスに乗せる技法を多用して描いた絵画でした。庭にニワトリを数羽飼っていらっしゃいました。だから一貫して先生の絵は見てきていますよ、小学校1年から日展を見に行っています。
富井:先生の作品が出品されているから、見に行かなきゃいけないのですね。
彦坂:そうですね。展覧会は見ているし、描いている所も見ている。それから団体展だから、上の先生がいるわけで、誰だったかわかりませんけど、その方に見せて批判を受けて、絵を直すとか、そういうこともしていたわけですけれども。その愚痴も聞いています。小さなキャンバスを並べて、小品を描いているのも見ていますが、売り絵の媚びの臭いがあって、嫌な気がしました。
富井;じゃあ、やっぱり他のアーティストの絵を見たりしていたわけですよね、そうすると。
彦坂:見ています。日展ですから東山魁夷、橋本明治、杉山寧、高山辰雄などですね。
ただ小学校の3年生から、三宿小学校の図書館に行って、とにかく『世界美術全集』をよくめくって見ていました。フェルメールも惹きつけられて、しげしげと見ていたのを今も覚えています。ただ何を見ているかっていうのはかなり問題で、やっぱり西洋美術を見る時、女性の裸がありますよね。半分裸を目当てに見ていましたね。文学もそういう傾向はあって、旧漢字で『昭和文学全集』を読んでいましたが、大人の小説の面白さは、性的な部分があったからですね。
富井:お家にあったのですか。
彦坂:病気がちだったので、小学校1年2年のほとんど学校は半分も行ってないので、暇ですから。だから布団に寝て杉の天井板の木目を見つめているか、小説を読んでいました。たとえば川端康成の不倫小説である『千羽鶴』を読んでいて、親に見つかって怒られています。旧漢字で読めるようになって、もっとも読めない字は飛ばして読んでいるわけですけれども、大人の小説を読んでいました。
その頃遊んでいることを思い出すと、ほとんど女の子と遊んでいました。
富井:妹さんと遊んでいたとか。
彦坂:いや、妹と遊んでいるという記憶はほとんど無いですね。遊んでいたはずですが……近所の子たちと、いわゆる仮装行列みたいなものです。変身ですよね、何か色んな服着て変身するみたいな遊びをやっていて、ちょうどその頃に美輪明宏(丸山明宏)が登場してきていて、シスターボーイという言葉があって、私はシスターボーイだって言われて結構いじめられたのですよ。非常に女性的な男の子でした。極度に痩せていて、あばら骨が出ていました。
富井:赤ちゃんの時はわりとふっくらしていましたけど、ここのあたり小学校低学年あたりだと思うのですけど、随分痩せていて。ここでスケッチしているのですかね、どこか旅行に行って。
彦坂:祖母と母親と一緒に、塩原とか、奥日光、五色沼、伊豆半島にも良く行きました。夏は、千葉の鋸山とか、長野の小諸の上にある薬師館に避暑に行っていました。
富井:そういうのはやっぱり中学に行ってから。
彦坂:避暑は、小学校の頃からです。それからもう一つやっぱり重要なのは、ベビーブームの世代であるということですね。だから小学校1年生に上がった時の最初の日に、まず1クラスが60人超えているのですよね。62、3人いたと思います。それで一学年が12クラスとかそういうレベルです。
富井:一学年にですか?
彦坂:はい。
富井:巨大学年ですね。
彦坂:そうです。ものすごく大変ですよ。学校に収容できないので、2部制ですよ。午前と午後とで分けて。
富井:一年生が?本当に凄まじいですね。
彦坂:そうですよ。だからそういう中で、1年目の初日に、私が(学校に)行って、祖母が付いて来ていて、祖母のことを(普段から)「おばあちゃま」って呼んでいたので、「おばあちゃま」って言ったら、そのそばにいた子がからかって、「おばあちゃま、おばあちゃま!」って言ってからかって、その子がまたこう腕がぷくっとふくれているコブみたいなのがある子だったのです。
富井:それは筋肉が付いていたからでしょうか。
彦坂:筋肉じゃなくて、腫瘍みたいなものでした。腕がぷくーっとふくれているのですね。その子と殴り合いになりました。だから1日目で喧嘩です。
富井:やっぱり学校の時は図画工作とか、あと何か得意な教科はあったのですか。
彦坂:いや、私は基本的に高校3年直前までは、医者になろうとしていたのですね。
富井:子どもの時からですか。
彦坂:はい。だからむしろ理数系の人間なのですね。
富井:それは何か親からのインプットがあったからですか。
彦坂:一つは自分の身体が弱いということですけど、7歳違いで弟が生まれるわけです。これは血縁関係のある実の弟です。父親が違いますが、母親は同じです。弟の出産が青山の日赤病院(日本赤十字社医療センター)でしたけれども、一種の医療過誤であったと思いますが、つまり生まれる時に、母親がある程度高齢だったせいもあると思いますけれど難産で、弟の頭を鉄の爪でつかんで引きずり出しているのです。それで脳性麻痺になったわけです。ですから生涯首がすわらない状態でずっと生きていて。だから歩くことも、話すことも、手を使うことも出来ないという重度の運動機能障害者であって……。
富井:ひょっとしてこの写真ですか。彦坂さんが抱いてらっしゃる。
彦坂:そうです、これです。だからその弟がいて、事実上成長しない赤ん坊ですよね。それだけど大きくなって重くなっていきますから。そういう子どもがいるっていうことは、すごく家庭的には大変なことです。暗くなりますし、他人を家に招待も出来なくなる。だから弟の理不尽な運命を哀れんで、何度も泣きました。私は、1人で布団の中で泣いていた。だから今でもそうですけど、弟のことしか考えてないっていう面があります。解決不能のトラウマです。いつも弟のこと考えていた。だから普通の意味で、人生の意味とか、そういうものを考えた時に、そういうまあボロ雑巾みたいにして存在し続けた弟の事を考えています。本人の責任ではないですからね。自己責任といって、不幸を本人に押しつけることも出来ない。本人の責任ではなくて、そのくせ頭が悪いってものでもないのですよね。だからしゃべることもできないくらい運動神経も悪いけど、知的には優れた子でした。まあ幅は極度に狭いですけどね、チャイコフスキーしか音楽は聞かなかったですから。その理由ははじめ分からなかったのです。あとでチャイコフスキーを勉強して分かったのですが、チャイコフスキーが、孤児や可哀想な動植物を理解し、その弱いものへの深い愛情と共感を日記や手紙に書いているというのです。しかも聾唖(ろうあ)の障害がある少年を同性愛的に愛したそうです。弟は、そういうチャイコフスキーの愛を聞いていたのでしょうね。
だからそういう弟がいて、だから医者になろうとするわけですよね。いわゆる医者って結構美術が好きなので、趣味で絵を描いたりする人もすごく多いのでね。まあ少なくとも友人関係であった……。名前が出て来ないですけど、嫌いだと名前が出て来ない、恐ろしい(笑)自殺しちゃった人ですけど、清水誠一(1946年—2010年)さんっていう。あれも同じ歳なのですよね、1946年生まれで、彼自殺しちゃいますけど。もともと医大で、新潟医大に入ってから美術家に転向していくわけですね。(1967年新潟大学医学部中退)その清水となんかも繋がっていくのは、一つは同じ年に生まれているということと、それから医学をくぐっているということで。私なんかはだから始めに全てありきで、今でも医者になろうとするわけですね、今でも。だからそれで色々トラブル起こすわけですよ。つまりまあ医学的に見ちゃうわけですよね。その日本の現実を。例えば今だったら、岡本太郎さんが優れたアヴァンギャルドだという風に信じるっていうことに、私なんかやっぱり抵抗感があって。世界美術史の中に置いた時に、1950年代で、アメリカ抽象表現主義とフランスのアンフォルメルの時代ですよね。岡本太郎の極彩色の漫画にすぎない絵をアヴァンギャルドって言うのかというのがありますよね。本人はアヴァンギャルドだって思っているわけですけれども、国際常識的には無理です。しかし日本の国内ではアヴァンギャルドであると信じられた。そういうのはやっぱり日本社会そのものとか、日本の美術界というものが、重症の脳性麻痺の病気に見えるわけですよね。
しかし日本の美術界は一方にまとも性も持っている、今ですと「ポロック展」、(「生誕100年ジャクソン・ポロック展」愛知県美術館 2011年11月11日~2012年1月22日/東京国立近代美術館 2012年2月10日~5月6日)は、愛知県美術館の学芸員の大島徹也さんのご努力で大変綺麗な「ポロック展」にできたと思うのだけどね。私は日本ではポロック展は開催できないと思っていたので、よく実現されたと思います。
でも、その「ポロック展」を見ても、僕の友達関係はみんな「ポロックつまんない」って言うわけですよね。そうするとそれはやはり病気に見えるわけです。一種の発達障害とか知的障害とか、人格障害とかそういうレベルですよね。まず人格的には、そういう人は、とにかく万能感に満ちていて、全てを自分が決済するわけです。だから自分より上の美術家がいるとか、過去に優れた画家がいるとかということを認識しないわけですよね。自分がいいと思わなければ、よくないっていうわけですよ。自分にわからないものが存在するわけですよね、世の中にはね、いくらでも。でもそういう自分の外部への気持ちが無いのですよ。万能感の中に立てこもることがアーティストだという定義が日本の現代美術界にはあるわけですよね。だからそういうことをされると、しかも『ジャクソン・ポロック』(美術出版社)を書いた美術評論家の藤枝(晃雄)さんと親密に付き合って来たAに、「ポロックよくない」って言われると、かなり頭にきますよね。だったらポロックと彼の絵を比べて分析してやろうと思うけどね、どちらが優れているか。だって私と前ね、延々と飲んでいる時だって、セザンヌとマティスどちらが良いみたいな議論を(したのだけど)、私はあまりそういう議論をしたくなかったのだけど、彼は結構しかけてきて、そのセザンヌの誠実さみたいなのをすごく言ったわけですよ。それがポロックの絵画の誠実さっていうのはすごいと思うけども、そういうものを彼は見えないわけですよ。私はやっぱり怒りがあるのね、そういうことに対してね。この怒りは、その作家個人に対してではないのです。何故にそういう“見えない”ということが起こるのかという、そういう構造が明らかでない事に対して怒りを持つのですね。文明社会や、そこに生きる個人を包む構造が、こういう理不尽な結果を生み出している。
富井:そういう形でシリアスにアートを見て今でもおられるわけですけれども、高校3年になって初めて要するにアーティストになろうと、医者ではなくてアーティストになろうという形で将来を考えられたわけですね。
彦坂:はい。まあ単純に、高校2年の末か3年の頭かな、3月くらいだったと思いますけれど、また肋膜炎が再発して、その時は結構人格的な崩壊が起きるわけですね。
富井:もう高校生ですからね。シリアスですね。
彦坂:うん。まあ、そうするとかなりキリスト教的な神の裏切りを感じるわけですよね。大した自殺未遂じゃないけど、自殺未遂しているわけですね。そして老子を集中的に読みます。その結果、だったらまあ簡単に言うと、遊び人になるか、みたいな。そういう、本当に遊び人になろうという自暴自棄的な決断をしたのです。
富井:それで、アーティストですか。
彦坂:そう。小学校一年から油絵を描いてきているから、逃げる場所が美術になったのですね。それでその時には、それでまだ持っているはずですけど、延々と1枚の絵をね、ふた月くらい描き続けるのですね。
富井:オイルですか。
彦坂:そう。毎日絵が変わっていくのですよ。
富井:オイルだから、描き変えられますよね、毎日。
彦坂:いや、オイルだと描き変えられません。油彩の制作技法的にはまずいです。油絵は、一日描いて、一週間くらいかけて乾かして、また一日描き重ねて、また一週間乾かす。乾くというのは油性ですから空気中の酸素と結合して乾くので、時間がかかるのです。したがって乾いた上に描き重ねていくものなのです。乾かさないで描き重ねるのは、やってはいけないことなのです。それを松本英一郎(1932年—2001年 独立展を中心に活動)っていう先生が見ていて、「彦坂まるでカラーテレビだな」って言ったのですけれども。
富井:それは、高校の時の先生ですか。
彦坂:美術の先生(東京都立駒場高等学校教員)です。都立駒場高等学校というのは、複合高校でして、普通科の他に芸術科と、体育科が設置されてあったのです。しかし今は、東京都立芸術高等学校という、独立した存在になってしまっています。ちょっと話を戻しますけど、小学校の時はさっきも申し上げましたけど、つまりいわゆる普通の落ちこぼれの美術家ではなくて、理数系を進むタイプですから、成績も別にそんなに悪いわけではなかったのですね。むしろ学級委員をやったりして、優等生タイプでした。もともと昔の写真見てもそうですけど、普通の意味で一流タイプの人間なわけです。そういう風に来ちゃっているから、中学1年生くらいまでは、病気が出て来ないまでは、非常に普通のエリートタイプの人間なわけですよね。それで中学2年になる時に、肋膜炎で結局病院に入院するわけですね。中学2年はだから1日も学校行ってないわけですね。最初に清瀬にある東京都立清瀬小児結核保養所に入ったのです。それで10日くらいいたと思うのですけど。松林の中にあって、空が青くてきれいでした。本人は面白かったですけどね。結核のそういう男の子、女の子がいっぱいいるわけですよね。そうすると子どもたちだから、夜になるとね、色々食べ物持って来て食べたりするのですよ。それでそこで初めてプロセスチーズを食べました。夜中によくわかんない暗闇の中で、チーズ食べさせられて、石鹸みたいなものだと思ったけど。
富井:それまで食べたことなかったのですか。
彦坂:無かったですね。私の世代っていうのは、そういう意味で言っておくと、まず、ちょっとこれもまた戻りますけど、まず電気冷蔵庫がない世代ですから。多分小学校2年くらいだと思いますけれど、氷の冷蔵庫が家に来た時、かなりはっきり覚えている。氷屋が毎朝氷を届けてくれる。洗濯機も、洗濯槽のみの一槽の洗濯機で、洗濯機傍についていたローラーで絞るタイプのものでした。小学校3年で初めてテレビを見ますね。
富井:白黒ですよね。
彦坂:はい、白黒で。だからそれまではテレビを見たことなくて、それで小学校の受け持ちの先生が床屋さんの息子さんだったので、そこにテレビがあるっていうのでわざわざ先生の家に行って、何かジャングルの中に入っていく30分のアメリカ製のテレビドラマを見て、それがすごく怖かったですね。私の世代は、たくさんモノクロ・テレビでアメリカのホームドラマとか、あとはスーパーマンとかそういうものを見ていくわけですね。
もう一つ大切なことは、ラジオドラマ世代なのです。そのテレビを見る前から。だからまずラジオだと「笛吹童子」(1953年1月5日~12月31日NHKラジオ放送」、アイヌを舞台にしたドラマの『コタンの口笛』(1958年6月1日~8月31日、14回の連続ドラマ、 NHKラジオ放送)。もっとあったのですが、そういうNHKの一連のラジオドラマを聞いています。民放ですが『少年探偵団』(ニッポン放送で1956年に放送されたラジオドラマ)、『赤胴鈴之介』(1957年にラジオ東京 (現TBSラジオ)で、当時小学生の吉永小百合や藤田弓子、当時15歳の山東昭子が出演。)『銭形平次』(文化放送で1952年から5年間、月~土の週6日のベルト連続放送された。現在でもラジオドラマの最長記録。)それから「ターザン」っていうのを、TBSラジオが毎日やっていた連続ラジオドラマで、私は「ターザン」大好きでしたね(ネット検索では、詳しい情報はありませんでした。)。今日私が問題にする《野蛮》と《文明》の問題は、この(エドガー・ライス・)バローズの『ターザン』に起源があるのですね。ラジオドラマだけでなくて、文庫本でシリーズを、たぶん全部読んでいます。「ターザン」、それから「ロビンソン・クルーソー」、「地底旅行」とか大好きでした。
富井:それもラジオですか。
彦坂:「地底旅行」はラジオじゃないです。(ジュール・)ヴェルヌの小説です。これとですね、バローズの『地底世界ペルシダー』という同じような話がありますが、この二つに大きな影響を受けています。この自分が立っている地面の下に、別の世界があるのですよ。後年ですがフロイトの発見した無意識とか、ユングの集合無意識というものにも、同じような意味で興味を持ちました・
『ロビンソン漂流記』は、(イギリスの小説家ダニエル・)デフォーの小説です。幼いときから、次第に高学年になっていく段階で、次第に大人の本へと、レベルの違う翻訳で何段階もかけて読んでいきました。「ロビンソン・クルーソー」の影響は大きくて、一人で無人島を生きていくという設定は、ワンマン・アーミーというか、集団行動よりは、一人で全てやって闘うという姿勢として、今も私の片側に残っていますね。私は小さな集団を幾つも作ってきていますが、一方では自分一人で全てをやっていくという面が強烈にあります。
あと、幼年期に影響を受けているのは落語ですね。その当時は郭話をラジオで平気でやっていたのですよ。遊郭にあがって、女性と一晩過ごしてどうこうっていう、今は放送できないレベルの艶笑話が、ラジオで普通に流れていた。親に隠れて、ラジオのスピーカーを耳にくっつけて、艶笑落語を聞いていました。私の小さい頃っていうと、赤線がまだ廃止されていなかったのです。赤線廃止の(ニュースは)モノクロ・テレビで見ていますね。今日が最後っていうのを。
富井:1957年ですね。昭和32年。
彦坂:SPレコードが家にたくさんあったので、「ワンさん待ってて頂戴ね」という「滿洲娘」(服部富子)とか、「父よあなたは強かった」という戦中の軍歌とか、広沢虎造の「清水次郎長伝」ですね、そういうものを子供のころに聞いて育っています。話はもどりますが、落語だけではなくて、ラジオでですが一龍斎 貞丈などの講談も聞いていたし、だからそういう江戸文化の伝統っていうのは子どもの頃に受けているわけです。だからなんだけど、柄谷行人の夏目漱石論(『漱石集成』、1992年)が嘘に見えたのです。夏目漱石全集も二度買っていますけど(筑摩書房/1971~73、岩波書店/1993~2004)、全集を丁寧にあたっていくと、柄谷さんの書いていることは嘘なのですね。事実関係が違いすぎる。夏目漱石の中には非常に江戸文学の伝統が強く生きている人なのです。もともと正岡子規から俳句を学んでいた人です。最初の小説の『我が輩は猫である』を発表したのは子規の主催する雑誌『ホトトギス』ですから、決してイギリスに留学したからっていって、シェイクスピアの影響を受けてとかそういう話じゃない。それを全部バタ臭くさせちゃうわけですね、柄谷さんというのは。だから例えば『夢十夜』(夏目漱石、1908年7月25日から8月5日まで『朝日』で連載)の中で、子どもを背負っていって、その重みの話が出てくるのだけれども(第三夜)、全集に当たっていくと、夏目漱石はその小説についての話を『朝日新聞』に、これは怪談話だということは書いているので、それをシェイクスピアで理解するというのは、まあ面白いっちゃ面白いですけれども、意訳すぎるわけですよ。私から見ると、柄谷さん自身に伝統的な日本文化の教養が無いっていう風に見えるのね。お父様が元々大地主で、マルクス文献が本棚にずらっとあったっていう。だから本棚だけのマルクス主義者。現実行動は何もしない安全な革命家だったのですね。『AERA』の「現代の肖像」にそういうことが書いてあったのですけれども、そういう父親を持った育ち方をしているからバタ臭いのかもしれません。そういう意味で言うと私は日本的なのです。平安時代の四大絵巻は好きだし、源氏物語や、枕草子は大切なのです。
小学生の時に私は結核性の腹膜炎と肋膜炎で日赤の病院に通っていて、そこで天皇にお会いしたのですね。天皇の行幸があって、敗戦直後の全国巡幸ですよね。あれ結構強く覚えています(作家による校正段階での注:昭和天皇による全国巡幸のスケジュールをチェックすると、東京にいらしたのは昭和21年2月から3月の頭なので、私はまだ生まれていません。ですから私はお会いしていないはずなのです。ウーム、唸りますが、幼い時のなんらかの記憶を自分で神話化していたのでしょうね)。
日本は1975年を過ぎると今の日本になっていきますけれど、それ以前とはかなり違うのです。だから若い人が昔のニュースフィルムを見ると、(その当時の日本はまるで)東南アジアだと思ったと言うといいますけれど、そのくらい変貌しているのです。私はですから東南アジア的な日本で育っているのです。
それで中学校にはいります。世田谷区立富士中学校です。学区域的には母親が教師をしていた新星中学校であったのですが、それを意図的に富士中に変えています。中学1年は元気な子どもなのでした。ところが中学2年の時に肋膜炎で清瀬の小児結核保養所に入りました。それで親は心配したわけです。
富井:合宿場に出したみたいなものですものね。
彦坂:そう。まあ、清瀬は松林ですごく綺麗な所だったですけどね。明け方になると群青色に空が明けていって、その空の思い出がありますけれど。
富井:空気が綺麗な所に作られているわけですよね、基本的には。
彦坂:はい。でも母親には危機感があって、それで私をそこから一週間か10日くらいで出しちゃって、東京世田谷の馬事公苑の近くの関東中央病院っていう、これは公立学校共済組合の教員の組合の病院です。そこに移した。そうすると(患者が)子供はいなくて大人だけで、しかも公立学校の先生たちばっかりなのです。それが1960年。だから中学2年生で大人の中にいたのです。大人の中で、1部屋が4人ですが、それは24時間の合宿状態で、仕切りの壁も塀も何もないですよ、カーテンがあるだけです。カーテンを閉めれば閉められるけど。しかもそういう部屋が6つあって、天井には仕切りがないままに24人の大部屋のひとつになっている。音はだから筒抜けの世界です。そこに1年間入院していたわけです。
時代は1960年安保闘争の時代です。学校の健康な先生たちがデモに行って帰りに病院に寄ってくる。「今日は怖かった」とか、それを聞いていたのですね。それで病院の待合室にあるテレビを見ていたら、これはライブで、浅沼さんが殺されるのを直にテレビ中継で見た(浅沼稲次郎暗殺事件 1960年10月12日)。「テロだ!テロだ!」ってみんなが言って、それで「テロ」って言葉も初めて聞いたのですね。そういう時代です。
その時に、とにかく1年も(病院に)いて、自分でも危機意識があるので、ずいぶんと本を買いました。公立学校の先生たちの病院ですから、本屋さんが定期的に行商に来たのです。それで『筑摩書房 世界文学全集』とか、『講談社版 世界美術全集』、それから同じく講談社版『日本近代絵画全集』を買ったわけですね。あと『世界の歴史』(筑摩書房)も買っています。
富井:それって自分のお金で買ったのですか。
彦坂:親のお金ですけどね、買っていくわけです。重要なのは、写真集ですけど『決して忘れはしない』(1961年)という、アウシュビッツの記録写真集を買って。やっぱりこれは強烈でした。それから同時に日本の、これはカッパブックスですけど、『三光作戦』っていう本も出たので、これも買っています。
富井:細菌戦争の話ですか。
彦坂:それは日本が中国大陸に侵略した時に三光作戦っていうのをとって。三つの光って書くのですけど、殺し尽くし、焼き尽くし、奪い尽くし、奪光(槍光)、殺光、焼光っていうんですけど。その作戦をとったということを告発した本で。これは読んだのですが、どう言うわけだか今持ってないですね。それであの本はあっという間に発売禁止になっちゃった。でも読んだので、非常に強烈に覚えている。中国人を丸太だって言って1人1人を1本2本って呼んでそれで生体実験していく。そういうのを読みましたね。それでまた話が飛んで申し訳ないですけれども、そういう経験が下敷きにあって、高校3年の時に、さっき医者になることを断念したということを言いましたけど、一つは病気の再発なのですけど、もう一つはね、遠藤周作の『沈黙』。『沈黙』を読むと、あれは『沈黙』かな……あっ『海と毒薬』(1958年)。『海と毒薬』で、捕虜にした米軍兵を、生体実験するという小説で、かなり衝撃強かったですね。自分がその場にいた時に、生体実験に参加しないっていう、その保証はないっていうモラル的な衝撃みたいなのがあって、医者になることを、それだけではないのだけど、病気という(理由が)明らかにあるのですけど。もともと東大医学部は無理だろうって思っていたけれども、千葉大の医学部を目指していたのです。まあ別に病気が再発したからといって、そのまま受験すればいいのだけれど、私の世代というのはさっき言ったように人数がもの凄く多いので、非常に過当競争の世界なのですよね。まあそういうことでできないってあったのですね。
もう1回中学2年に戻ると、その時にキルケゴール(セーレン・オービエ・キェルケゴール Soren Aabye Kierkegaard)の『死に至る病』っていう哲学《象徴界》を読んでいるのですね。それで中学2年の時に肋膜炎に最初になっているのですね、高校は再発ですけど。それはだからかなり酷かったのです。1番酷い時期は、ひと月間吐いて、水も飲めないような状態で、熱も42度続いていて、割れるような頭痛で、とにかく白血球が異常に増殖していったので、それで医者がもうこれ以上無理だから、とにかくわかんないですけどお腹開けましょうって言って、開腹手術をするわけですね。そうすると、腸結核と慢性盲腸があったわけです。その慢性盲腸は、小学生の時に何度もお腹痛くて家に帰っているのですよ。だからそういうことを抱え込みながらずっと生きてきているから、とにかく大変は大変なのですね。それで、手術で助かって死ななかったわけですけれども。手術するとその後もまた、夢というか、夢をとにかくやたらに沢山、病気の中で見るわけですよね。目を開けて物をたくさん見ていますからね。だからまあ幻覚ですけどもね。
あと問題は、一つは、さっき言った『日本近代絵画全集』ですよね、その近代絵画全集は結構読んだので、日本画も洋画も、そんなに、評伝批評的なレベルでの知識は付いちゃっているわけですよね。結局魅かれていくのは一つは靉光なのですね。それからもう一つは富岡鉄斎。これも絵で見て魅かれたということよりも、伝記というか、見出しとか、そういう中で、文章で魅力のあるものが書かれていて、まあそうかなと思うわけですよね。それで見ることになるから、だから病院を出てからだと、中学段階だと、美術館巡り、それからギャラリーですね。昔ですから、まだ国立近代美術館が京橋にあって、その裏に南天子画廊さんがあって、今の南天子画廊とはちょっとやっぱり違っていて、そういう靉光とか、鶴岡政男とかそういうものやっていたし、あと上野の不忍池のそばに不忍画廊ってあって、あそこもそういう「新人画会」の作家の作品が結構出ていて、だから出たっていうと見に行ったのですよ。
富井:じゃあ一応洋画系を見ていたということですよね、近代洋画を。
彦坂:そう近代洋画を。特に自分が生まれる直前の人たちです。新人画会を本気で追いかけていました。だからそれを私は正しかったと思っている。例えば松本竣介だと、高校3年の時に松本竣介の画集が出まして、これも買っています。だからそういう少年だから、全体にとにかく美術的には早熟なわけです。それからあと高校だったですけれど、『日本絵巻全集』が出ていて、それは図書館で全部を見てます。その中で『餓鬼草紙』に強く引きつけられています。もちろん『源氏物語絵巻』も好きだし、『鳥獣人物戯画』も好きだったけれども、『餓鬼草紙』をすごいって思っていました。だから最近でも今皇居美術館空想って作った時に(『空想皇居美術館』彦坂尚嘉、五十嵐太郎、新堀学著、2010年)日本の絵巻物で、四大絵巻以外でも優れたものってあって、中でもやっぱり『餓鬼草紙』はすごいと思います。だからそういう基盤があって……。
富井:そういう所まで遡るのですね。
彦坂:だからその、良くも悪くも中学・高校段階で私自身の教養ができていて、しかももう高校受験する時にもまた病気になったので、高校受験をだから1段階(レベルを)落としたのです。元々都立青山高等学校を受験しようとしていたのだけど、都立の高校の最上位校である都立日比谷高校まではやれないのだけど、青山はやれるというレベルだったのですけれど、受検一ヶ月半前くらいに高熱を出して、これどうなのだろうっていうのがあったので、それで都立駒場高等学校を選択したのです。東京都目黒区大橋にある学校で、東京大学教養学部からすぐで、井の頭線の駒場東大前下車の場所です。三宿の自宅からも歩いても行ける近くにありました。実際の通学はバスでしましたけれども。
都立駒場高校というのは、戦前の第三高女っていう高等女子教育の名門中の名門でした。そこに落としたと言っても、女子では都立難関校の一つでした。
少なくとも入学の時点では私は1番で入いっています。しかし、入学してしまうとダメでしたけれども。とにかく女子校の名門ですから、女の子たちの勉強はすごかったです。では、なぜ入学試験段階では1番で入ったかというと、数学の問題が難しかったのですよ。最後の問題が難解ですごかったのです。それ私は解いたのですよ。だからトップ取ったのです。
いわゆる美術家っていうのは、普通は数学弱いとか、物理学と化学が弱いとかっていうけれど、私は物理化学の成績は上位にいました。特に化学の授業と試験は難しかったですが、私は食らいついていました。だから美術家としては毛色が違っていたのです。
富井:その間、ずっと清原啓一さんについて油絵を描いておられたのですよね。
彦坂:そう。
富井:それはやっぱり好きだったからですか。
彦坂:わかんないです。まず中学生段階で、同じ学年に画家の奥山民枝さんがいたのです。彼女は中学校から一緒だったと思います。高校になると、美術部に入って画家の遠藤原三(1947年—日展会員、光風会監事)氏と出合います。彼は現役で多摩美術大学に入って、私が浪人中に関東中央病院に入院しているときに、親身に見舞いに来てくれて、一緒に版画詩集の同人雑誌『外』を三冊出版しています。この時の遠藤氏の恩義は、今もありがたいことだと思っていて感謝しています。その遠藤原三に親しくしていらしたのが、都立駒場高校にいた学生ではなかったと思いますが、女流画家協会の画家:遠藤彰子(1947年—安井賞、紫綬褒章受賞作家)氏だったわけです。わかります?遠藤彰子っていう具象の油彩画家です。
富井:ちょっとわからないですね。
足立:武蔵野美術大学の先生です。
彦坂:そうです。だから高校段階から遠藤彰子は知っていたわけです。今も遠藤原三が彼女の夫君のはずなので。それで駒場高校の段階で遠藤原三を清原先生のとこに紹介して、一緒に行っていたのです。
富井:そうなんですか。
彦坂:はい。遠藤原三はそのまま日展の道を歩んだのです。
富井:なるほど。
彦坂:うん。だから多摩美術大学の学生の時に、日展に入選しています。多摩美の中でも大きな話題になりました。だからまあ清原先生に付いて行ってしまったのです。それに対して私は清原先生と決別していった。すり替わったのですね。その面でも、私は遠藤氏に感謝しています。
遠藤原三氏の話で言えば、遠藤氏はとにかく高校段階でミケランジェロに私淑していて、ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂とか、ミケランジェロの絵画の大型全集本を買っていました。何冊も見せてくれて、「すごい、いい」って言っていたわけです。その辺から私とは絵画観が違っていたわけです。私ははその時には、ミケランジェロの絵画をダメだとは思わなかったけれど、とにかく見せてもらって勉強はしていたわけですけれど、それで本物も見に行きましたけれど、ミケランジェロのあのシスティーナ礼拝堂の絵は、絵画としてはダメなわけです。ミケランジェロは、絵画を実体的に描く絵画の描き方で、だからティツィアーノとかミケランジェロの描き方っていうのは、社会的には大人気で大きな影響を、今日のルシアン・フロイトにまで与えますが、絵画の正論ではない。少なくともああいうものがダメだという考え方は、絵画論の中にはあるということです。だからルシアン・フロイド(Lucian Freud 1922年—2011年)の絵もそうですけど、絵画展開を画集で見ると、すごい説得力がありますが、しかしあれはダメだという、そういう価値観はあるのですね。レオナルド・ダ・ヴィンチは、ああいう風には描いてないですね。それはだからしょうがないですよ。どちらが良いかっていうのは争いだけれども。例えばティツィアーノの絵というのは、一種のごまかし絵なので、単純に言えば窓の向こう側に広がる空間というのは、あれは描けてないわけです。だからそういう意味でミケランジェロに惚れていっちゃう絵描きっていうのは、当然ペンキ絵になっていってしまうから、その限界性っていうのはあるわけです。
そういうわけで、高校の話に戻ると、1番大きいのは、都立駒場高校は普通科だけではなくて、保険体育科と、芸術科があったのです。(注:都立駒場高校芸術科は、1972年に都立芸術高校に分離独立)。
富井:なるほど専攻としてということですね。
彦坂:はい。私も遠藤氏も普通科でしたけれど、だけど芸術科があるから、美術の専門学科がったのです。それで高校なのに美術館まであったのです。
富井:そうなのですか。
彦坂:はい。その美術館が、牧野虎雄(1890年—1946年)の牧野虎雄記念館でした。牧野虎雄というのも奇妙な画家で、大正期の、今の私の言語判定法で言うと21流なのですけれども(笑)、とにかく奇妙な日本画化した洋画ですけど、結構装飾性が強くて、だけどある範囲で人を魅了する力がある作品でした。それの大きな木を描いた絵が食堂にばーんとあって、結構本格的な牧野虎雄記念美術館ですよ。そこで、結構何回も、10回はしてないですけど、6回くらいまで私の企画で、美術部の展覧会や個展をやりました。
富井:個展ですか。
彦坂:個展。ただ芸術科の方からは、すごい批判があって看板壊されたりしましたけれど。だって芸術科の方は、全く受験用の絵を描いているわけで、みんなセザンヌ調でしたから……。
富井:セザンヌですか、その頃は。
彦坂:うん、もうセザンヌですね。セザンヌ的な絵がオンパレードで。こちらは違う絵を描いていたわけですね。
富井:どんな絵を描いていたんですか。
彦坂:そんなはっきりした傾向を持っているわけじゃないけれど、結局清原さん系統の絵を描いているから、清原さんの口癖は「デコラティブになるな」って言うのだけど、でも人間っていうのは言っていることと、やっていることが違うわけです。デコラティブになるなって言っているってことは、デコラティブな絵を描いているわけですね。だからそういう傾向は持っていましたね。結局美術に行こうと思って、高校3年生になると美大への受験を考えるから、まず病気が再発しているのですけれども、また入院するっていうのが嫌だったわけです。前は、中学校では1年休学していますから、休学終わってそのまま進学してもいいよって言われたのだけれど、それは今の学校制度でも進学できるっていうのをこのあいだ橋下(徹大阪府知事)の関連で教育の記事読んだら書いてあったりしたけれど、やはり落とすべき(落第)ではないのかって橋本徹は言っていたわけですね。私の場合は先生からそのまま進学してもいいですよって言われましたけども、勉強してないのだから、1年もう1回ちゃんとやりますって言って。だから同じ学校でそういう留年をするから、すごくひどいことになったのです。だからもとの同級生は上に行っているわけでしょ。そして自分が一年遅れでなった同級生は一年下の子たちなので、仲良くならないでしょう。それから身体弱いから、体育っていうのはほとんど見学だったのです。みんなが行進の練習をしていて、ザッザッザって隊列が来るのです。そうすると私は砂場に座ってただひたすら地面を見ているのです。じぃーっと見ている。これがね、私の良くも悪くも美術の原点なのですね。地面をじぃーっと凝視し続けているとね、地面が段々膨らんでくるのですね。凝視すると、視覚が変わるのです。だからそこから続けて話をすると、実は私自身は村山知義さん(1901年—1977年)の影響が結構強いのですよ。何の影響かというと、村山知義が戦後に『忍びの者』(全5冊)を書くのです。そして忍者ブームの中にできるのです。記憶の中では小学生の時のはずなのですが、実際には私が中学生の時ですね。当時山本薩夫監督の『忍びの者』(1962年)は見ていなくて、テレビの『忍びの者』(1964年)は毎週見ていました。でも記憶だと、子供の漫画雑誌の記事のところに忍者の訓練が書かれていて、それを夢中で読んでいて、訓練のまねごとをしています。それはテレビで『忍びの者』を見る前だったのです。もともと忍者ものは戦前の立川文庫の『猿飛佐助』とか『霧隠才蔵』ですから、もしかすると村山知義の前に、忍者ものの記事が子供の雑誌に出ていたのかもしれません。確認していませんが、記憶の中では、忍者のなり方っていうのを、だから雑誌で言うと『少年』とか、『冒険王』とかで読んでいたと思うのです。
余談ですが『少年マガジン』『少年サンデー』の創刊号から読んでいました。だから私自身は『チャンピオン』は創刊号を知らないし、『チャンピオン』はろくに読んでなくて、『ジャンプ』になるともうついていけなかったですね。一切ついていけないです。今でもそうですけど『ジャンプ』の絵って見られないですね。ついでに言えば、『ビックコミック』は、『月刊コミック』の創刊号から読んでいます。
話を戻すと、だから忍者に興奮して、忍者の訓練をする。だから例えば植物を植えて、毎日(その上を)飛んでいると、植物が段々高くなっていくから、高く飛ぶ練習になるとか。そういうノウハウはそのまま信じてやっていくのですよ。
富井:本当にやっていたんですか。
彦坂:まあ、たかがしれたまねごとですが、いろいろ後年までやっています。簡単に言うと、1番大きかったのは、あとで話す、例えばバリケード時代に警察に逮捕されていますけど、その場合でも『忍びの者』の教えの通りに、まず逃げるときには、「付け髭をつけちゃいけない」って言うのです。「付け髭はばれやすい」。だから始めに髭を生やしておけ。「逃げる時に髭を剃れ」って言うわけです。だから髭も伸ばしたし、髪の毛も伸ばして、髪の毛はものすごく長くて、これくらいでまで長くしていました。
富井:肩までじゃなくて、腕まで(長かったんですね)。
彦坂:それで黒眼鏡かけて、徹底的にガードをしていました。とにかくデモをしても、公安が写真撮影しているのです。その頃は、石を投げている写真を撮られるだけで起訴されてしまうと言われた時代だったのです。
それでだから一応私の責任で桑沢デザイン学校の闘争の支援をせざるを得なくなって、その時には事前に易教で占いました。易の占いというのは六十四卦あります。易は、迷信では無くて、チャンスオペレーション、つまり偶然を使って反省するシステムなのです。占うと自分が逮捕されるって出たのですよ。ですから髭も全部剃って、髪の毛も普通の短さにきって、だから逮捕される準備をして出陣したのです(笑)。
富井:容姿が変わるわけですね。
彦坂:うん。だから逮捕されても、全然面が割れなかったのです。
富井:向こうが全然わからなかったということですね。
彦坂:はい。
富井:それは『忍びの者』の、極意ですか。
彦坂:はい、極意と言うほど大げさではないです。一週間完全黙秘して、まあ、結局は名前も言いましたが、警察は武蔵野美術大学の別の学生だと思っていました。
だからそういう調子で本気で訓練を、いろいろしたわけです。たとえば暗闇の中で色んなものを触って、触覚だけで物を認識するとか。
富井:それはどちらの方で、忍びの方でですか。
彦坂:忍びの方で。だから『忍びの者』でそういう影響受けて、そういう訓練を随分色々やったのですよ。
富井:じゃあ、地面を見つめるっていうのはそれですか。
彦坂:うん。だから地面を見つめているとね、膨れてくるので、それは何人かの美術家も同じようなことを言っています。地面だけに限りませんけど、何かを凝視し続けると視覚が変わるんです。だからそのことの重要性っていうのが、だから普通の人っていうのはあんまりよく見ないんですね、物事を、繰り返し長い時間をかけて凝視して見る。
ベトナム戦争に行った小説家いますよね。開口健(1930年—1989年)。あの人は食べ物ですけど、やっぱり自分がおいしいと思うものを食べた時には、とにかく2ヶ月でも3ヶ月でも毎日のように同じもの食っていくというのですね。そうすると味の底の底がわかるっていうのだけど、私は今も開高健の教えを続けています。近くのベトナム料理屋には、5年通っておなじものを食べていました。とにかくリピートしていく、凝視するということをやっていくと、ものが変わって見える。
岡本太郎が言う「縄文式土器はすごい」と言う意見ですけれども、私は新潟の十日町の十日町市博物館にある縄文式土器は繰り返し見に行ったのですね。そうするとまあ1回目は面白いですけれど、2回3回になると急速に劣化していくわけです。面白くなくなる。
アフリカの黒人彫刻も、繰り返しニューヨークのメトロポリタン美術館のロックフェラーが作った大コレクションを繰り返し見ていますが、1番目は凄く面白いですが、リピートに全く耐えられないのです。
だから何度見てもすごいねっていうものを大切にします。まあなんだって飽きることは飽きるのですけど、ただリピートに耐えていくものってあるのです。それが《真性の芸術》です。
耐えていかないものもある。普通は3回くらいでもうダメですよね。子どもを連れてディズニーランドに行った時、私はディズニーランド好きじゃないのですけれども、子どものために2回行っただけなのですけれど、上の子と下の子を連れて行った。ディズニーランドに入るとパレードが来るわけです。そうすると本当に面白いわけ。私も本当に面白いと思った。うわーこんなに面白いものがあるのかって思った。行っちゃった後に、子供に「面白かったねー」って言いましたよ。でもちょっと時間たつとまた来るわけです。子どもに「また来たよ!」って言うと「ふーん」って言って、その時はもうそんなに集中しないのですね。3度目にパレードが来たときには、もう子供は見ないのですよ。また来たっていっても、もう見ない。ああいう刺激っていうのはね、リピート効かないんです。刺激って、あっという間に劣化していくのです。だからエロ写真とかポルノ映画とかもそうですけど、リピート利かないのです。急激に劣化していく。だからそういう劣化していくものを芸術とは言わないっていうのは、私の基本的な立場なのです。
前にやっぱり某美術館の館長と、そういう話をした時に、「一度でも良いと思えばいいじゃないか」って言うからね。「そうすると某作家の作品が一時期10号で180万して、あっという間に業者間で15万くらいに落ちちゃうわけですよ。」と実名を言って実例を話しました。「だから本物の芸術と、偽物の芸術っていうのは現実に存在しますよ」という話をして、「そうやって価格が落ちてしまって、100万損失するのが良ければいいですけど」って言ったら、「それは困る」って言いうのね(笑)。
だから芸術作品っていうのは、一種の刺身のような生ものではないのです。どんなにうまい刺身でも、20年後に食うとまずいですよ。
富井:いや、食べられないですし、存在してないから(笑)
彦坂:芸術は生ものではなくて、ワインだとか沖縄の古酒、ウイスキーやブランディング、そして梅干しだとか、ああいう発酵性のある漬け物に近いところがあって、時間が経てば経つ程おいしくなっていくという性格があるのです。
芸術に魅了されるというのは、こういう時間を超えて行けるからですね。まあそうこうして病気が再発したから、美術家になろうと決意したのですね。もう1回1年過ごすのは嫌だったので高校終わってから病院に入院しようとすることにしたのです。3年の時は、すいどーばた(すいどーばた美術学院 以下、すいどーばた)に通っていたのですね。
富井:じゃあデッサンとかを、受験用に。
彦坂:受験用に。その時の先生が榎倉康二(1942年—1995年)だったです。
足立:1966年に榎倉康二さんにお会いしているということですね。
彦坂:榎倉さんがまだね、今私たちが知っているような作品ではなくて、その時に見たのは、日動系のグループ展で、「ルモン(山)」という展覧会があったのですよ。そこに榎倉さんが出しているって言うので、見に行ったんです。油絵で、何と言うかな、散乱したような鏡が割れたような比較的色の多い油絵だったのですけれども、それは見ています。ってそういう話をすると、榎倉康二は、嫌な顔されたんだけれども……。
富井:榎倉さんがね。そりゃそうでしょうけど。嫌な過去知られてるみたいに(笑)
彦坂:嫌な過去って、そんなにね(笑)問題になる絵ではないと思うのだけど。
富井:じゃあその頃から、だいたいまあいわゆる現代美術の世界にいる人たちと、知り合うみたいになったということですか。
彦坂:いや、現代美術を自覚的に知るのは、ですから高校終わって、それでもう1回関東中央病院に入院するわけですよね。その時に母親が、大量に1950年代の『みづゑ』を、持って来てくれたのね。
富井:古本屋か何かですか。
彦坂:いいや、母親の勤めていた中学校の図書館が蔵書を処分してしまったのですね。それをもらって来てくれたのです。
富井:(図書館が)新しいものを入れなければいけないから。それ(古い『みづゑ』)をじゃあ、お母様が持って来てくださったんですか。
彦坂:はい。そこでいわゆる東野さんの(東野芳明)『現代美術』っていう単行本ありますよね、あれの『みづゑ』でのオリジナルの連載ですよね。
富井:1960年ですね、それは。
彦坂:単行本になってまとまって出た時が1965年でしょう。
富井:この間見たら1961年の『みづゑ』を1冊取ったら、ポロックが出ていて、どうしてこんなところにポロックがあるのかと思ったら東野さんのテキストでした。だからそのことですね(注:東野芳明著『現代美術 ポロック以後』(美術出版社)の出版は1965年4月。東文研のデータベースで『みづゑ』の記事検索をして現代美術の特集が61年だったことを富井が確認した)。
彦坂:うん、そう。その東野さんの連載をかなり大量に見るわけですよ。それでジャスパー・ジョーンズも知るし、ポロックも知るし、ロスコ(マーク・ロスコ)も知るし。その記事を延々と読んでいたわけです、病院で。
(注:東文研のデータベースで検索すると、東野芳明の「ジャスパー・ジョーンズ《現代美術の焦点11》」は『みづゑ』685号1962年4月、「ジャクソン・ポロック《現代美術の焦点1、2》」は672号1961年4月と673号5月、「マーク・ロスコー《現代美術の焦点19》」は700号1963年6月。作家がこの連載で見た他の作家は、ファンタナ、ローシェンバーグ、デュビュッフェ、マーク・トビー、ニーヴェルソン、デ・クーニング、サム・フランシス、ゴーキー、フォートリエ、デュシャン、ティンゲリー、オルデンバーグ、リキテンシュタイン、タピエス)。
富井:病院でね。することないですからね。
彦坂:それはだから単行本になった、『現代美術』と違ってカラー図版がたくさんあるのですよね。
富井:すごいですよね。だって一応「特集ポロック」って書いてあるから、1961年に『みづゑ』でポロックの特集するなんて、何なんだろうって思って。それで私は見たんですけれども中を。そしたらポロックのあの髭面の顔(の写真)が入っていて、それでクラズナー(リー・クラズナー)、奥さんと一緒にいるのがあって、本当にカラー(写真)がじゃんじゃんありました。私、びっくりしました。
彦坂:大判の、しかも今の『美術手帖』なんかの印刷は、オフセットですけど、あれは凸版の原色印刷っていうものです。だから観賞できるのです。昔のカラー印刷は観賞できたのです。インク量が多いので、ジャック・ラカンが言う所のシニフィアン連鎖が成立するのです。鑑賞もできるし、意味構成が成立しました。しかし『美術手帖』は1980年代からかな、途中からオフセットにしたので、オフセットになると、カラーページは増やせますけど、インクの量が少ないので、安物の画像になって観賞性が喪失しました。それで情報だけになってしまったのです。
富井:その『みづゑ』をご覧になっていたんですね。
足立:50年代の日本の美術も、そこでお知りになったのですか。
彦坂:うーん、だけどあんまり日本美術の記憶は無いですね。惹きつけられたのはやはりアメリカ美術ですよね。圧倒的にアメリカ美術の情報ばっかりで。だからそれは私の現代美術入門であったのです。
富井:それは現代美術ですね。まさにね。
彦坂:だけどまだあれですよ、清原さんにはくっついていていましたね。
富井:確か団体展にも出品なさってましたよね。
彦坂:1回だけですね。だから病院を出て、健康になって、生き延びたわけですよ。それで多摩美(多摩美術大学 以下、多摩美)を受験しています。高校3年終わった時は芸大(東京芸術大学 以下、芸大)も受験しているのですが、石膏デッサンの試験で、当たった場所が悪い場所で、描くのが難しかった。それとね、もう一つ言わなきゃいけないのは、斜視だったのですね。小さい時から斜視だったのです。そのハンディを感じていたし、浪人中は病院に一年入院していて、受検のための研究所には全く行っていてませんでしたから。
富井:斜視なんですか。
彦坂:はい、斜視で、石膏デッサンやっているから、空間認識に限界があったのです。完全な立体視ができなかったのですよ。自分の欠陥を知っているから、それをカバーするために、空間捉えようとして、舐めるように描いていたわけです。それですいどーばたでのペインティングですけど、裸婦を描いたコンクールの批評で、トップまでいっているのですよ。そしたら先生の1人が、「いや、この花瓶のある台が描けてない」って言われて、それでばーっと落とされたのです。
富井:なるほど。でも描けてなかったんですか。
彦坂:それはそうですよ。だってその対象物の表面を詳細に追ってしか空間捉えてないから。完全に空間全体を立体視しできていないのです。どっかで漏れが出るのです。それで結局斜視を手術しようと思って。それで医者を探したわけですね。今みたいにインターネット無いから、本で探したのだけど。結局名医と呼ばれる井上医院をお茶の水に見つけて、そこに行って右目を手術しているわけです。メスが右目に近づいて切るので怖いのですけど、それに耐えた。あとはひたすら両眼視の訓練です。その時に両眼で見ることの意味というか、視覚というものの意味構成について学んでいます。だからさっきの忍者の訓練とつながっていくのです。
富井:それまでは見てなかったわけですね、両眼で。
彦坂:はい、そうですね。
富井:その時手術が出来たんで、初めて視覚がその時に変わったんですね。
彦坂:そうですね。それと自覚的に両眼視していくことを組み立てようとするでしょう。だから常に怯えがあるわけですよ。歳取ってきてもそうですけど、常に怯えがあって。
富井:また戻っちゃったらという怯えですか。
彦坂:戻ったらというか、だから例えばこの間『アバター』(『Avatar』ジェームズ・キャメロン監督, 2009年 3D映像)って三次元映画ありましたけど、あれだって三次元に見えるのかなって不安があるわけです。(笑)
富井:そういう風に思われるわけですか。なるほど。
彦坂:常にやっぱり努力があって、それでまあ見えているから問題はないのだけれど、訓練による自覚的な分、他の作家よりもデッサンの善し悪しや、空間が描けているかどうかの判断力は鋭くなっています。だから同時にこの間私の気体分子ギャラリー(「○○新作個展」2010年5月21日~6月1日)でやった○○さん(1981年—)の場合は、彼女は斜視で、そのことを私は知っているから、そのことは別に私は文章に書かなかったけれど、それでまあ、彼女のハンディを持ったペインティングの意味が分かるから、評価して展覧会をやったのだけどね。しかし結局彼女は、逆に斜視だから、自分の才能が無いと思ったのかもしれないけど、結局自分は美術家にはならないと言っていました。お父さんもお母さんも日本画家でいらっしゃるので、だからそれなりにその才能はあって、それとやっぱりその斜視の部分を補おうとするから、すごい努力が絵の中にあるのですね。だからそれは高く評価したのだけれでも、私の努力は無駄でした。別に今時は斜視は手術で治ってしまうのですけれどもね。
富井:もっと(斜視の手術は)簡単になってるんでしょうね、きっとテクニックなんかも向上して。
彦坂:はい、だからそんなに難しいことではないのです。手術が怖いだけです。だからもちろん若い時期に早くした方が良いと思います。だから私は自分の障害をそういう風に克服してきているでしょう。私の場合は、そういう病気の克服の連続なのですよ。
だからついでに言うと、例えば自転車に乗るっていうのも、昔は乗ってなくて。41歳で初めて自転車に乗れるようになったのです。自動車の免許は45歳です。それから51歳で初めてコンピューターをやったのです。それで今完全データ入稿できるところまできていますからね。私はもう本当に努力の人なのです。
その話で言うと、なぜそうなのかっていうことなのですけど、20歳の誕生日、それをだから高校の3年終わってから入った病院で20歳の誕生日です。その時に自分は才能が無いっていうのを痛烈に思ったわけですよ。どうしてかっていうと、関根正二(1899年—1919年)を知っていたわけです。講談社の『日本近代絵画全集』に収録されている関根正二の作品と評伝を読んでいるわけです。それで今も私は関根正二の作品を評価しています。言語判定法で芸術分析をして格付けしていってもいい作家だと思います。特に18歳くらい、高校生の時に描いていた絵はすごいですね。指導者が良かったと思いますけれど、大人になる前の寸前の時に超一流のものが発達するので、素晴らしい若描きです。その関根正二は20歳と3ヶ月で死んでいますので。それで自分が20歳になった時に、あと3ヶ月で関根正二にはなれないっていうのを、痛切に思ったわけです。(笑)
富井:それはかなり痛烈な自覚ですね(笑)
彦坂:だから私はもう才能では勝負しない。そういう決意をしたわけです。だから良くも悪くも学習、学習、学習を目指しました。今でも、よく勉強会をやりますけれども、私が若い人と接して、若い人が私から吸収することを大切に思うのです。しかし現実には、ぱっと泥棒していく若い人たちもたくさんいるのです。そして私との関係をまったく抹殺して隠してしまう。そういう人たちってすぐ落ちてしまうのだけどね。教えたことの本質的な意味を理解しないのですね。
だけど最近で言えば例えば糸崎さん(糸崎公朗 1965年—)の今度やる展覧会のための写真は、私は、見せられた私の方が驚きましたよ。おーって、いい写真だったのです。それは本当に私がどうこう教えたのではなくて、私から自分で吸収したものを本当に身につけて、写真が良くなっているわけですよ。そうするとやっぱり私は驚くわけです。私は良い作品が好きなのですね。良い作品を見ると感動するし、良いものは良いって言うわけです。まあ嫉妬することもないわけではないですが、あんまり他人を嫉妬はしません。時々はありますね。1番嫉妬したのはモンドリアンです。モンドリアンは本当に才能のある人だと思うけど。絵も内容もどんどんどんどん変わっていくのだけど、どれで描いてもすごいですよ。あれはすごい才能だと思うけれどね。
富井:まあ死んでしまった作家を嫉妬するくらいなら、大丈夫ですよね(笑)
彦坂:今話し損なったもので1番大きいのは、中学2年生、病院出て来てからやっていたのが、東京国立博物館等々美術館に行って、古い美術、特に国宝、重文を目で暗記していたのです。国宝や重要文化財の絵画は、見ても、中学生の私では、古美術は茶色っぽくて汚くて、良いか悪いかは分からないのですよ。しかし国宝とか、重要文化財と書いてあるのに惹きつけられるのです。きっと凄いものなのだろう。どうしようと思ったのですけれども、丸暗記するしかないと思って、見て暗記、暗記、暗記、暗記って頭の中で言って見ていたわけです。私はそういう態度取ってきているのです。ですから私の美意識を育てたのは東京国立博物館であり、国宝システムです。
大学になると、今度は関西の方まで行っています。日本美術の良いものは、圧倒的に関西にあるのですね。京博(京都国立博物館)とか、奈良博(奈良国立博物館)、そして大和文華館に、まだ当時は安かった新幹線でたびたび行っていたのです。とくに大和文華館は大好きだったのです。
それは学生時代に海外の作家と、どう戦うのかということを考えたのです。今の様には簡単に安く海外の良い展覧会を見に行けない状態だったので、見られないのですね。見なければ勝負にならなくなります。であるのなら、とにかく日本人は日本の中で1番いいものを見て、目を鍛えるしかないと思ったのです。
それからもう一つは、読売の海藤(日出男)さんが企画した展覧会をたくさん見に行ったのです。
富井:アンデパンダン(読売アンデパンダン展)は関係無いですか。
彦坂:アンデパンダンはもう終わっていて見てないですが、例えば「フォービズム100年展」(注:「マチスと野獣派展 色彩の勝利」1974年、会場:西武渋谷店ほか、主催:読売新聞社か)とかね。「ダリ展」(注:「ダリ展」1982年、会場:伊勢丹美術館、主催:読売新聞社ほかか)とか、「ピカソの版画展」(「ピカソ女性たち展:美と生命の賛歌,傑作版画1904-1968」1970年、会場:東急本店(渋谷)、主催:読売新聞社ほかか)とかですね。そういう一連のものは海藤さんだと思いますけれどね。
一番大きい影響を受けたのは、これも中学生の時ですけれど、クレーの展覧会があって、これは海藤さんかどうかわかりませんけれど、クレーの日本で開かれた一番大きな展覧会が来ました(注:「パウル・クレー展」(1961年、西武百貨店))。とにかくきれいで、夢を見るように取り憑かれましたね。それで家でクレーの絵を模倣して描いたのです。1枚だけですが。それを自分で見て、深く傷つきましたね。表面だけのマネで、本物とはまるきり違っていたのです。この経験は大きかったですね。
その展覧会では、クレーの中では例外的に100号くらいある三角形のピラミッド状の(作品)。(《Ad Parnassum》 100×126cm 1932年、ベルン美術館蔵)が来ました。あれはクレーの中で非常に例外的な作品なのですよね。クレーの作品というのは、観賞構造が、ほとんど《愛玩》で作られていて、あれは《対話》という構造になっていたのです。それで珍しい作品なわけですね。クレーはあまり《対話》の作品は作ってないわけです。だから基本的には小さな絵ばっかりで、《愛玩》という鑑賞構造になっています。
絵画には大中小があって、それは起源が違うのですね。大きい絵画といのは、壁画などの建築美術ですね。中くらいの絵画はタブローや掛け軸で、これは運搬用の流通美術です。小さい美術というのはミニアチュールで本の美術です。クレーの作品は、そういう本の美術に起源を持っている小さな美術っていう意味ですけどね。そういう絵なので、大きなピラミッドの絵画は例外的なのですけど、ネット上(の人気)で言うと、あれが上位に来るんですよ。だから結局芸術としては《対話》構造で描いている物を高く評価するという一般的な傾向があってかもしれません。つまり芸術とは何なのかっていう定義を見ていったときに、やはり《対話》という構造なのだていう考え方は根深くあると思いますけどね。
富井:それは芸術とは何かっていう問いで、もちろん彦坂さんが追いかけて来ておられるわけですけど、そうするとやっぱりそういう美術大学に入る前から、そういうものを意識する、あるいはしないで追いかけていたというわけですか。
彦坂:それはそうですよね。
富井:自分の才能が無いなら学習で、ということでね。
彦坂:関根正二という優れた夭折の作家に比べて、自分に才能が無いと言う認識は、ジャック・ラカン的な精神分析の認識で言えば、そこで私は子供の万能感を殺して、岡本太郎的な独りよがりの自己愛性人格障害から脱したと言うことです。子供の万能感を殺す事が重要です。子供の万能感を、自分の才能だと思い込む才能主義そのものが愚かなのです。カントの才能論は、少なくとも日本の中では愚劣化しています。病院に入院して、肋骨を切る手術をして、私はイニシエーションをくぐったのですね。大人になった。
私には常に苦痛があったわけですよ。弟の重度の脳性麻痺も大きいし、自分の病気も大きいですけれども、苦痛があった。小さい時からとにかく病気になって、天井じぃーっと見ているしかないわけですよ。そうすると天井が杉板で、その杉板の木目を延々と見続けてきたわけです。だから後からですけれど、ドイツ神秘主義のエックハルト(マイスター・エックハルト Meister Eckhart 1260年頃—1328年頃)の翻訳が、あれ90年代にならないと出て来なかったので、日本では、ただエックハルト系統だったものを、私自身が読んできているわけです。エックハルトというのは、あの(著書が)ローマ法王から焚書を命ぜられるから、本が無くなったのです。ところが隠し持っていた人たちが、エックハルトの思想の系譜を作っていったのですね。私が高校生段階だと、私、ブーバー(マルティン・ブーバー Martin Buber 1878年—1965年)を読んでいるのですね。ブーバーの『我と汝』(『Ich und Du』, 1923年)を読んでいて、ブーバーもエックハルトの系譜なのですね。それから内村鑑三(1861年—1930年)なんですね。内村鑑三を中学2年から読んでいるのですよ、わたしは、だから病院にいた時に、絶望していますから、キルケゴールの『死に至る病』を読んでいるのと同時に、病院に牧師が来ていて、それが内村鑑三の無教会主義だったのですね。それで無教会主義者になりました。だから、内村鑑三の英語執筆の『余は如何にして基督信徒となりし乎』の日本語訳ですが、中学段階で読んでいます。それからキルケゴールの『死に至る病』は、世界文学全集に入っていたということで、筑摩の世界文学全集、赤い表紙のものですが、これを読んでいます。もう、自分は死ぬと思っていましたから。ラジオのNHKの第二放送、あそこでキルケゴールの『死に至る病』のレクチャーが、丁度あったんですよ。それも連続の講義であって。それを聞きながら読んでいたのです。そのキルケゴールの『死に至る病』は、その後もとにかくその後も何度も読んでいます。8回くらい読んでいます。それから『反復』という小説も惹かれました。何度も読んでいるということで、キルケゴールと、それから老子と、老子の影響が精神的にものすごく大きいです。それとまあ聖書ですね。そういうもので、かろうじて自分の精神を支えて来たわけです。
富井:聖書は新旧両方ですか。
彦坂:いや、基本的にはもう新訳ですね。だからそれも内村鑑三ですよ。内村鑑三の聖書解釈で読んできています。まあだからそういう背景でもって美術を追っかけてきてしまっていると、日本の美術界とうまくいかないのですね。教養が違いすぎるってなるのです。だから作家と接したときにとにかく……。たとえば△△△(1947年—)だと、私が美術の話をしようとすると、「そういう話はしたくない」って言うわけです、それは、はっきりと言う。
富井:今高校3年まで、浪人時代まで多分いったんじゃないかと思うんですけれども、大学入るところまではせめて今日行きたいです(笑)
彦坂:そうですね。
富井:1年目は東京芸大を受験されたのですよね。
彦坂:芸大受験だけです。それで浪人中は受験勉強全然しないで、病院にいましたから。それで病院から出て、それで一つは100号と、50号の絵を描いて、それを初めて光風会に出品するのですね。それで100号の作品は入選するのですけど、三段掛けの1番上に掛かっていたのです。
足立:どんな絵ですか。
彦坂:あのね、女性がいて、それが立っているのですけれど、その前に静物があって、後が風景であるものです。人物画と静物画と風景画の複合形態ですね(笑)。
富井:三点盛りですね。
彦坂:はい。本人はかなり意気込んで描いたのです。あと、静物の50号だったかな。だけど団体展に初めて出して、三段掛けに掛かっているのを見て、ある意味ではどっかで傷ついているのですよね。それで戻って来た絵を、庭で火つけて焼いたのです。焼いているのじーっと見ていたのだけど。
富井:作品を焼いたり破壊するのは、その時が初めてですか。
彦坂:この最初の一回しか無いですよね、自覚的には。そのときは本当に一種のイニシエーションだったというのだと思いますけれど(笑)まあ今から言うとね、もったいなかったなと思いますけどね。残すべきだったと思いますけど。
富井:回顧展するときに困りますね。
彦坂:はい、写真も無いですものね。だから実はその後も無いわけじゃないですよ。ウッドペインティングの最初の絵が、潰ぶしているのですよね。
富井:それは壊れてしまったんですか。
彦坂:そうじゃなくて、描いて、仕上がった時に、やっぱり自分がもたなかったのですよね。今から思うと、何があったかというと、本当にそこに超一流から163万8400(次元)が出現していた。だから言葉で言うと、結局「底が抜けて黒い海が見える」というのが、私の『反覆』(『反覆/新興芸術の位相』1974年)って本の……。その病院に入っているときに、3冊か4冊詩集出しているのですけれど、その中に入っている詩です。詩としては《原-詩》《詩》《反-詩》《非-詩》《無-詩》があって、《想像界》《象徴界》《現実界》《サントーム》《ディープミステリ》《ノーネイム》《越境》《未知》《その先》《死》の10界があります。誰も私の詩は評価しませんが、おぞましい詩ですが、しかし、良い詩です。その「底が抜けて黒い海が見える」っていう感覚は、だからずっとあるわけです。しかし、それが最初のウッドペインティングに描けて、それに耐えられなくて、潰して、きれいきれいな『森』という作品になった。この『森』と言う作品も、《原-芸術》《芸術》《反-芸術》《非-芸術》《無-芸術》があって、10界があります。そして《15超高温プラズマ》になっています。良い作品だと思いますが、これも日本人には分かりにくい。誰にも分からないのかもしれません。
だからその、ここの多摩美術大学に入学してもそうでしたけれど、大学というのはやっぱり動物園に見えるわけですよね。どうしても。その動物園に入るのを、汲々として喜ぶ価値観があるでしょう。
富井:大学って、大学の先生自体が動物園っていうことですか。
彦坂:つまり《文明》の制度って、動物園の檻なのですよその中で充足してしまう。
富井:学生さんではなくて。
彦坂:学習することの意味は別にあると思うのです。学習を否定しているわけではないですし、大学という一般教育を無用だと否定しているわけではない。それは美術館もそうですけど、美術館を否定しているわけじゃないですけど、その美術館の中に芸術が存在するのかって言ったときに、その美術館、私は好きだから、美術館にたくさん通いますし、何も美術館の中に芸術が存在しないって言っているわけではないですが、美術館の中に芸術が存在しているわけではないのですよ。
神に祈る場合もそうだけど、教会に入って祈るということはしますけれども、しかしキリストが神になっていくのは教会の中ではないですよね。それから日本の高野山でも、比叡山でもそうですけど、山岳信仰の人たちが山の中を走っていたのであって、お堂の中に神がいる、仏がいるっていうことは一かけらも言ってないです。仏像があっても、あれを仏という風には言わないのです。元々仏教は、仏像を作ることは厳しく禁じられて来たから、400年くらい経ってですからね、仏像を作るっていう風になったのは。仏に祈るっていうことはあったとしても、それは本質としては違うのだよね。だから「底が抜けて黒い海が見える」っていう意味は、そういうことですけど……。まあ足下にね、ひたひたとね、波が来るっていう感覚がすごくあったのです。だからそれは何なのだろうって思って来たのだけど、最近の格付けが増えて来ると、去年の3・11(東日本大震災)を体験すると、急速に認識が展開していくわけですよ。あれは底が抜けていくということでしたね。
富井:文字通り。
彦坂:文明の外部が出現したわけです。文明が、つまりどんなに大きな堤防を作っても、決して黒い海を完全には阻止できないわけです。巨大なビルが根こそぎ抜けて、ばーっと倒れていて、引き抜かれているのが、まず五十嵐太郎さんが驚いてその写真見せてくれたのだけど。本当に実物見に行っても驚きました。これはどうしようもない。それで4階まで津波が来ている所なんか見ると、これは逃げられないなって思って。とにかく津波の来る所には住めない。
『反覆/新興芸術の位相』に収録した「敗北の宣言」で、「絶対に負けてやらない、自殺はせん、戦いをやめない、復讐してやる、絶対に負けてやらない、絶対負けてやらない、自殺はせん」っていう(ことを書いた)。そういうような決意みたいなものが、今も続いているわけだよね。こういう言い方は良いとは思わないけれど、でもまあ当事者としてはしょうがないね。だからどうしたって、自分の出生の問題とか、弟の出生の問題とか、そういうものは一方的に受動的に引き受けるしか無い。自分は時代を選んで生まれて来るわけじゃないだけど、それも受動的にそれを引き受けさせられるわけですよね。自分の責任では無いのだけレッドも、それにも関わらず、それを受動的に引き受けることで、それを全て自己責任にかえて引き受ける以外に生き得ないわけです。
他人のせいにするのはダメなわけです。社会のせいとか、他人のせいとか、最終的にしてはいけないわけです。それがモラルです。《象徴界》というのは、そういう理不尽さを承認するところに成立するのです。全てを自己責任に回帰させなければいけないわけでしょう。だからそういう戦いの問題になるから。それが最終的に高校生の時もそうだけど、一種の神への絶望の問題へと重なってくるわけで、信仰っていうのは同時に神への絶望の問題なのですよ。
だから芸術っていうのは私から見ると、神と格闘していく作業なのです。だからそれは、神は世界を作ったかもしれないけれど、それはだからあくまでもデザインに過ぎないっていう風になるわけです。神は芸術を作らなかった。だから自然は私の芸術論の中で言えば、言語判定法的にはではデザインなのであって、だからあくまでも個人……受動的に生まれて、受動的に死んでいく個人の、その格闘の問題として、芸術っていうのは存在するのです。だからそれ以外の方法が無いっていう風に私なんかは思ってしまうわけです。
共同体に回収できる部分が無いとは思わないですが、今だってあると思っているけれども、しかし社会制度そのものは、結局芸術を認識できないのではないかっていう(気持ちになる)。
今度の「ポロック展」でも非常に強烈にあったのは、グリーンバーグ(クレメント・グリーンバーグ Clement Greenberg 1909年—1994年)がポロックの芸術を理解してなかったのだという風におもえたのですね。私は。あの大島さん(大島徹也 愛知県美術館学芸員)の展示の中で、良いと言った作品が、決して彼の最高の作品ではない。
富井:グリーンバーグが良いと言った作品がね。最高じゃないっていうことですよね。
彦坂:はい、そうです。ポロックは初期は超一流ですが、その次は六流の作品を作っていて、それをグリーンバーグが評価したのです。その後再度ポロックは超一流になります。それから世間が最終的にポロックの昔返りとして、良くないって言った黒いポーリング・ペインティングですが、私の芸術分析ですと、あれの方が作品は良いと思います。だからポロックは見事に、初期にあった作品の良さを自己回復していくわけですよ。良い仕事だと思います。ポロックは自分に対してすごく忠実に展開していると思う。それを、だから社会自体は認識できないわけですね。それは今でも認識できないわけだよね。
だからそういうことに対する見切りというか、社会自体は《真性の芸術》を認識できないということ。《真性の芸術》は社会には無理なのだっていう風に、私は思うわけです。認識できるのは、社会性の外部にいる個人ですね。
だから芸術のわかる人も個人としては少数いるけれど、しかし批評家とか、学芸員とか職業性も持つと、世間体に配慮するから《芸術》を認識できなくなる。だからそれは昨日「日本ラカン協会」の学会の読書会だったけど、そこでやっていても、結局ラカンが50年代に社会の形成っていうのはどういう風にきているかっていう世間体の分析をしていくわけですけど、それはあくまでも本質的理解ではないところで繋がっていくという構造を出して来るわけですね。まあシステムとして、社会自体が《真実》はわからないシステムなのですよ。つまり《文明》というのは公共という表層で成立していて、プライベイトとして外化している私生活の中に住む個人の真実は疎外しているのです。
だから社会の場合、常にマイナス1だって言うんですけれど……。4人なら4人の人がいて、限定された組織があったとしましょうね。そうすると4人の内のマイナス1で、マイナス1が何か無いといけないのですよね。
富井:仲間はずれですね。
彦坂:そう、仲間はずれ。そうするとその仲間はずれに対して、彼ではないということで、残りの3人が結びつくわけですよ。そういうマイナス1。それが天皇制を形成しているって言うわけです。天皇は特別な人だっていうその部外者を1人作ることによって、日本社会が結束を作っていくという。そういうシステムを作っていったという論理を延々やっていて、まあ新しい理論じゃないですけどれども。1950年代くらいの理論だと思いますけれども。まあだからそういう世間体の論理の中で作動し続ける限りは、芸術そのものはやっぱり見えないのですよね。まあ見えのないなら見えないでしょうがないという風に思いますけれども。
富井:じゃあそのしょうがなさ辺りを次回からお聞きすることになるんじゃないかと思います。
彦坂:どうもすみません。迷路みたいなしゃべり方しかできなくて(笑)。